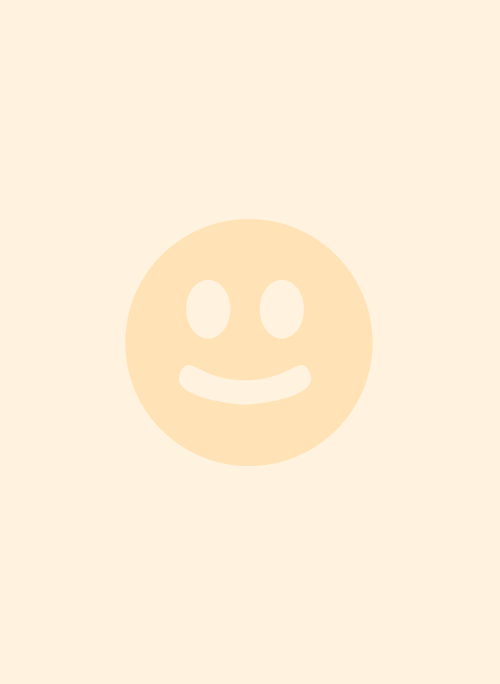「お、落ち着いてください!確かに前は部活ばかりで、前までの成績では清架なんて志望するのも失礼なくらいの成績でした…」
おい担任。
嘘でもいいからもう少しオブラートに包んでください。
「ですよねー」
なんでそこはすぐ納得するんだ。
息子を信じる心はないのか。
「でも、最近は勉強もすごく頑張っているんですよ。それこそ、清架高校を狙えるくらいに。」
「は?そ、そんな、うちの息子はバスケバカなんですよ?いや、もはやただのバカです!清架なんて…」
「…まだ、絶対に大丈夫とは言えませんが、挑戦してみる価値は十分にあります。それになにより、本人のやる気がここまで成績を伸ばしたんですから、本人を信じてあげてもいいと思いますよ?」
黙って聞いてりゃ二人して勝手なこと言いやがって。
バカバカ言い過ぎだぞおい。
「俺は清架に行くことしか考えてないから。」
「またあんたはそうやって自分の実力も知らないで…」
「大丈夫。清架入るために今まで勉強してきたんだ、意地でも合格してやる。」
「本人もこう言ってることですし、お母さんは見守って、支えてあげてくれませんかね?」
「いや、むしろ何もしなくていいから、受験させてくれ。」
「…本当に、清架高校なの?」
「なんでそんなに嫌がるのかを教えて欲しいわ。」
「だって、あんな頭良い高校なんて…」
「心配いらねーよ。黙って受験させて。」
「わかったわよ…落ちたら承知しないからね!」
うん。落ちる気ないから問題ない。