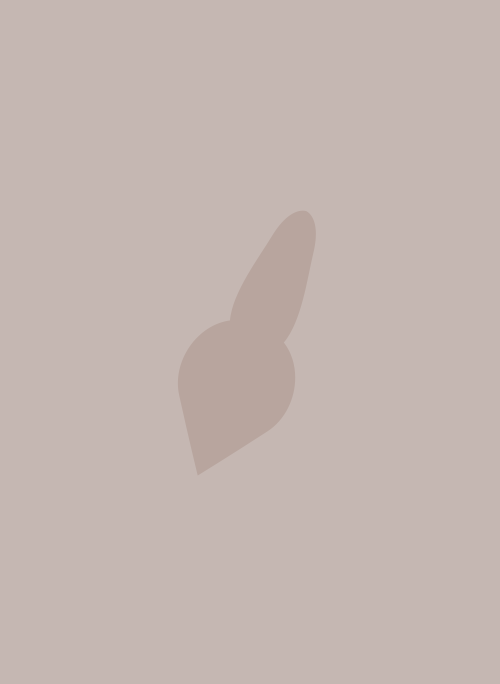「あったとしても、それはお前の気にしなくて良い話だ。」
だからもう帰りなさい。
親父はそう言ってタクシーの扉を再び開ける。
「なんで隠すんだよ!」
「もう出してください。」
運転手に呼び掛け、
それを聞いた彼は不安げに俺を見ながら車を走らせた。
「なんで…こんなの、おかしいだろ…」
そう呟いた声は、
肌寒くなった風の中に消えた。
半ばよろめきながら
自室のドアを開ける。
倒れこむようにベッドに腰掛け、ドサッと乗せていたジャケットが落ちた。
それと同時に落ちる、もう1つのもの。
――これは……
大野亜矢子のマンションの合鍵だった。