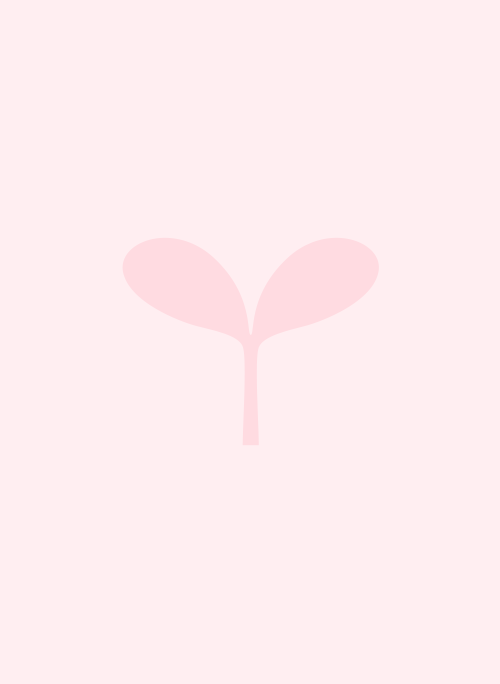そしてレイルは自分より背が低い彼女へと視線を落としながら言った。
「それにしても昔、お嬢様は首都で暮らしていたんですね」
「……ふん、もう忘れたわ」
言葉とは裏腹に、懐かしく思い出すようにウルベは穏やかな口調で道の脇へと視線を移す。
レイルはそんなウルベを無言で見つめた。
そしてそんな少女の日傘を持っている手に気が付くと、不思議そうに声を出した。
「いつもしているのに、グローブを着けないのですか?」
ウルベはそれで気が付いたとばかりに自らの手を見つめた。
「ああ、どうやら忘れてきてしまったようだ」
そして少女はそう言いながら茜色に染まった眩しい空を避けるように日傘の向きを変えた。
その握った白く、小さな手には似合わず、大きな傷跡が残っているのをレイルは横目で見つめると、静かに微笑んだ。