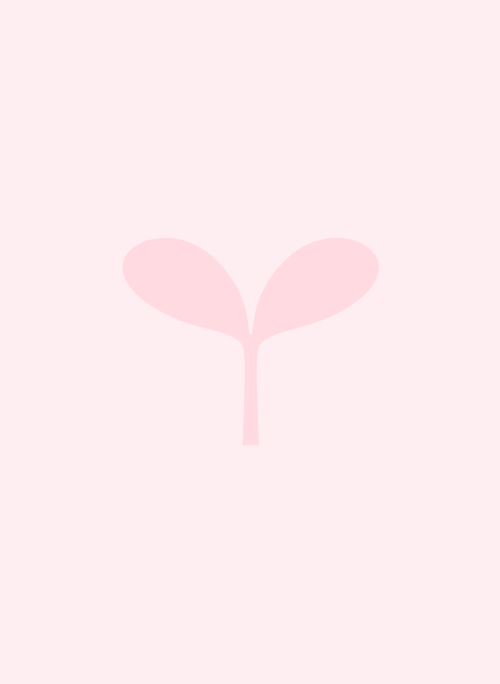二人はキッチンへとトレイを運ぶ。
「僕、捨て子なんです」
ホームにまだ声変わりをしていない少し高い声が響く。
セシルは俯きながら歩いた。
後ろにいるレイルの表情は読めない。
「街のとある帽子屋店の前に段ボールが置かれていて、そこに赤ん坊の僕が入っていたそうです」
声は低すぎる訳でもなく、高くもない。
セシルは何も聞かずにただ静かに聞いていた。
「雪が降った日だったそうです。けれど弱った僕は泣き声も出さず、前を通る人は見向きもしなくて……あ、後で帽子屋の旦那さんに聞いたんですけどね?」
ふふ、とレイルは小さく笑う。
「それでさすがに見兼ねたその帽子屋が中に入れようとした時、ウルベ様が拾って下さったんです」
セシルは振り向いた。
少年の顔を見つめる。
少年は穏やかな顔をしていた。
「あの方は命の恩人なんです」