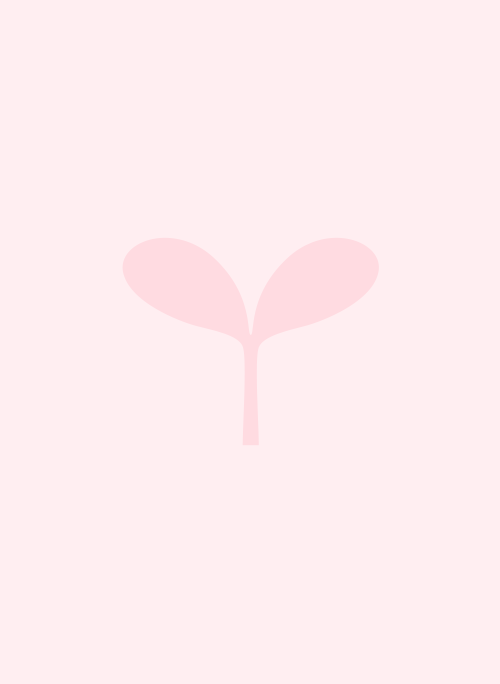そうだ、私は一体いつまでここにいるつもりなのだろう。
俯いて高鳴る胸の鼓動を感じながらセシルはリュエフの質問を自らに問いかけた。
期限なんて、考えた事はなかった。いや、考えないようにしていた、というのが正しいのだろうか。
もともと期限なんかはなかったし、彼は何も言わない。
しかし"永遠"は存在しないのだ。
それはこの世の理(ことわり)であり、絶対だ。
そんなことは分かっている。
だからセシルはわざとその"別れの時"を考えないようにしていた。
出ていけとも、ずっとここに居ろ、とも言わない彼にセシルは不安を感じていた。
それは二人だけしかいないこの屋敷で、この何とも言えない気持ちを言える者はいなかった。
今、ここでこの気持ちを言っていいのだろうか。
複雑な感情がいろんな絵の具が撒き散らされたキャンパスのようにセシルに重くのしかかっていた。
リュエフは何も言わないセシルを見つめながら、ついに沈黙を破った。
「ここは君の帰る家やないで」