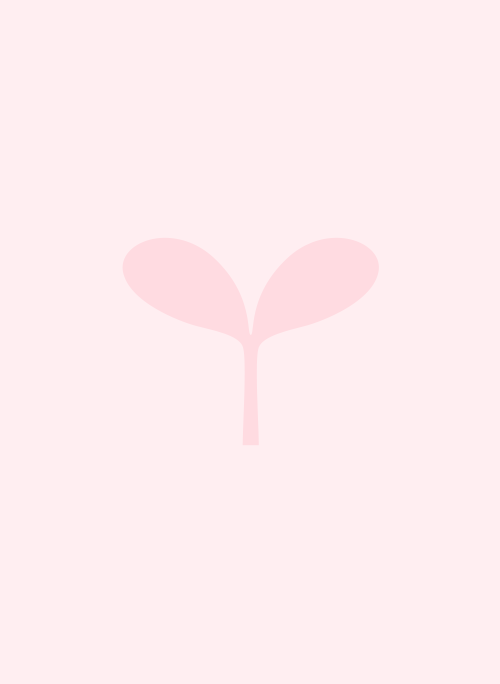幼かったラルウィルでも言葉の意味が理解出来た。
幼い、といっても人間の子供とは違い、ゆっくりと長い年月をかけて成長していくこのヴァンパイアの少年は、人間の時間の流れではもう四十年は故に越えていた。
心と体の成長は歪みを産む。
しかしラルウィルはもう母の言いたい事が何となく分かるようにはなっていた。
ラルウィルは握っている花をじっと見ると歯を食いしばった。
母はそんなラルウィルに気がつくと、彼に向き直り、またいつもの優しい微笑みを浮かべた。
「でもね、せっかくラルウィルがそうやって母さんの事を思ってくれてるんだからその気持ちとしてこの花は飾らせてもらうわね」
ラルウィルはそっと顔を上げると、「うん!」とまた笑みを浮かべた。
――…
「母さん、今日は母さんの好きな赤い薔薇が咲いたよ」
「そう…」
ベッドに座った母は色を失ったような目で窓を見つめていた。