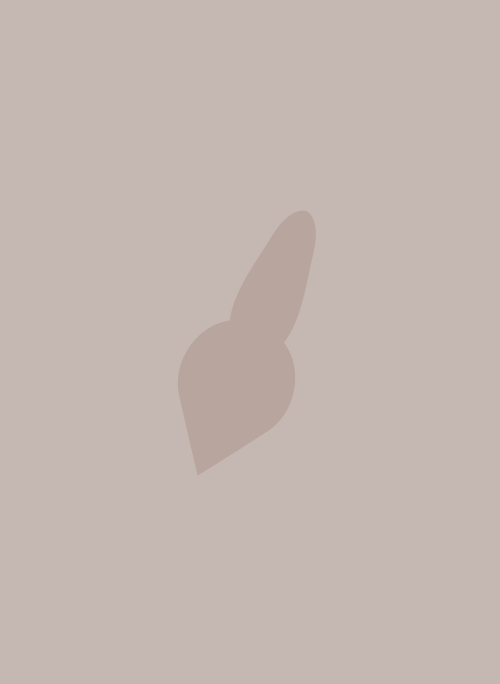「ねえ、好きな子とかいるの?」
『教えるわけないじゃん』
「いいじゃない、そんな風に言われたら余計気になるわよ!」
子供のようにハシャぐお母さんに、だんだんイライラし始めてた。
早くこの場から抜け出したい。はやる気持ちと苛立ちを抑え、『いない』と嘘をついた。
「え~、本当はいるんじゃないの?」
『いないってばぁ』
それでも何とかして聞きだそうとするお母さんに、もう限界だった。
『もう、同じ事言わせないでよ!!いないものは居ないんだから!!』
「怒らなくても……」
『たまに帰ったからって無理に関わろうとしないで!』
それだけ言うと居間を出た。おばあちゃんがいた気がしたけど、そのまま階段を駆け上った。
「あの子も大人になったのね……」
微かにそんな声が聞こえた。
『はぁー……また言い過ぎた』
大きく息を吐き、ドアを閉めると制服のままベッドに飛び込んだ。
『ん~……』
しばらくボーっとしてると、カバンの中に香水があるのを思い出し、起き上がった。
『……あった!』
取り出した香水を両手で握ると、枕にひと吹き掛けると机の目に付く場所にそっと置いた。
甘い匂いが部屋を満たし、心を満たしていく……
つまらないこの部屋も今日は好きになれる気がした。
少し背の高い本棚に、参考書ばかりの机。
クローゼットに入りきらなかった服が仕舞ってあるタンスを見て、再びベッドに倒れた。
『いい匂い……』
目を閉じると、仁の笑顔が見えた。
制服な事も忘れ、お母さんに言った言葉も忘れ、誘われるまま眠りについた────
『教えるわけないじゃん』
「いいじゃない、そんな風に言われたら余計気になるわよ!」
子供のようにハシャぐお母さんに、だんだんイライラし始めてた。
早くこの場から抜け出したい。はやる気持ちと苛立ちを抑え、『いない』と嘘をついた。
「え~、本当はいるんじゃないの?」
『いないってばぁ』
それでも何とかして聞きだそうとするお母さんに、もう限界だった。
『もう、同じ事言わせないでよ!!いないものは居ないんだから!!』
「怒らなくても……」
『たまに帰ったからって無理に関わろうとしないで!』
それだけ言うと居間を出た。おばあちゃんがいた気がしたけど、そのまま階段を駆け上った。
「あの子も大人になったのね……」
微かにそんな声が聞こえた。
『はぁー……また言い過ぎた』
大きく息を吐き、ドアを閉めると制服のままベッドに飛び込んだ。
『ん~……』
しばらくボーっとしてると、カバンの中に香水があるのを思い出し、起き上がった。
『……あった!』
取り出した香水を両手で握ると、枕にひと吹き掛けると机の目に付く場所にそっと置いた。
甘い匂いが部屋を満たし、心を満たしていく……
つまらないこの部屋も今日は好きになれる気がした。
少し背の高い本棚に、参考書ばかりの机。
クローゼットに入りきらなかった服が仕舞ってあるタンスを見て、再びベッドに倒れた。
『いい匂い……』
目を閉じると、仁の笑顔が見えた。
制服な事も忘れ、お母さんに言った言葉も忘れ、誘われるまま眠りについた────