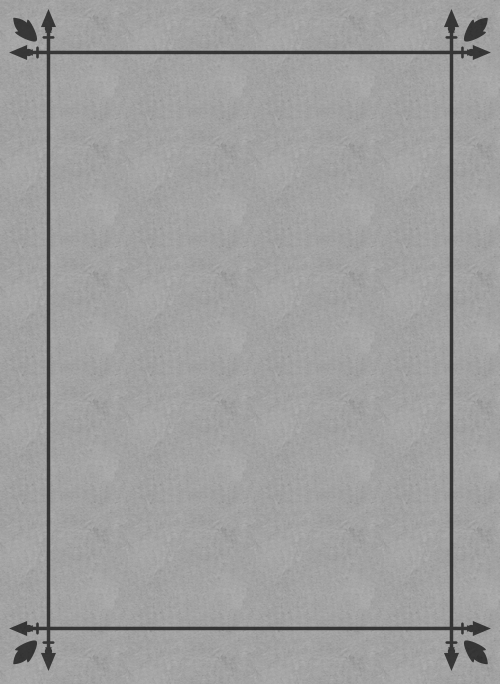しばらくして、兄貴と部屋へ戻ってきた彼女の目は真っ赤に充血していた。
泣かせてしまった、悲しませてしまってどうすれば良いのか分からないまま、俺の傍に寄ってきた彼女。
『……おはよう。城戸くんと同じ高校の同級生だった本城です』
彼女はそう言ってにっこり笑った。
涙は、流れていなかった。
『私たち、結構仲良かったんですよ』
本城さんは、初めて病院に来てくれた日にそう言っただけで、他は何を聞いても流して答えてくれなかった。
先生に言われたのか、それとも兄貴達から口止めされてるのか分からないけれど。
何を質問しても答えてくれなくて。
自力で思い出して、とでも言うように悲しそうな表情を向けるだけで。
でも、その表情も一瞬で消えて笑顔に変わってしまう。
俺の見間違いだった?と思うほど、一瞬に。
仲が良かったなら、俺がどんな人間だったのか詳しく知っているはずなのに。
仲が良かったはずなのに、俺の事を『城戸くん』と呼ぶ。
俺が敬語で本城さんに話し掛けるからか、彼女も俺に敬語を使う。
まるで、昔の俺とは違う今の俺を新しい人間として割り切って接しているようだった。
俺も、昔が分からないから、そんな接し方しかできなかった。