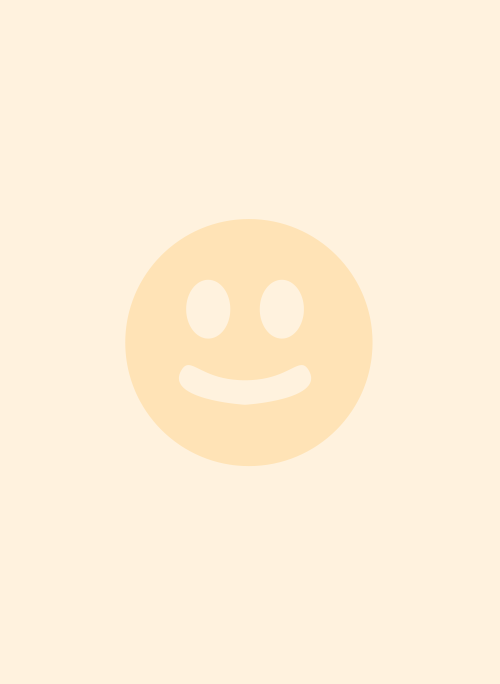「僕は彼女を忘れられなかった。いろんな女の人と付き合ったけれど……彼女を思い出してしまうんだ」
「それじゃあ、塩谷さん、結婚は?」
確かに見舞いに来ても彼の家族に会った事はない。しかし、二十年も一人の人を想っていたなんて事があるんだろうか?
「してないよ。と言うよりは出来なかった。本当は結婚を意識して付き合った事はあるんだ。でも、どうしても彼女を忘れられなかった。二十年だ。二十年間、一日だって彼女の事を忘れたことはない。それなのに、どうして僕はあの時、彼女がいなくなってホッとしてしまったんだろう。どうして彼女の手を離してしまったんだろう……」
泣きそうな表情だった。ずっと胸の奥にしまっていた想いが流れ出すのを、塩谷さんは苦しそうな表情を隠そうともせず、我慢していた。本当は、ずっと誰かに曝け出したかったのかもしれない。
それが、死を直面して『僕』という第三者に話さずにはいられなかったのだろう。
同じ過ちを犯さないように、と。
もしかすると、彼は僕に自分の若い頃の姿を重ねて見ているのかもしれない。
「加藤君、君は神様はいると思うかい?」
「それじゃあ、塩谷さん、結婚は?」
確かに見舞いに来ても彼の家族に会った事はない。しかし、二十年も一人の人を想っていたなんて事があるんだろうか?
「してないよ。と言うよりは出来なかった。本当は結婚を意識して付き合った事はあるんだ。でも、どうしても彼女を忘れられなかった。二十年だ。二十年間、一日だって彼女の事を忘れたことはない。それなのに、どうして僕はあの時、彼女がいなくなってホッとしてしまったんだろう。どうして彼女の手を離してしまったんだろう……」
泣きそうな表情だった。ずっと胸の奥にしまっていた想いが流れ出すのを、塩谷さんは苦しそうな表情を隠そうともせず、我慢していた。本当は、ずっと誰かに曝け出したかったのかもしれない。
それが、死を直面して『僕』という第三者に話さずにはいられなかったのだろう。
同じ過ちを犯さないように、と。
もしかすると、彼は僕に自分の若い頃の姿を重ねて見ているのかもしれない。
「加藤君、君は神様はいると思うかい?」