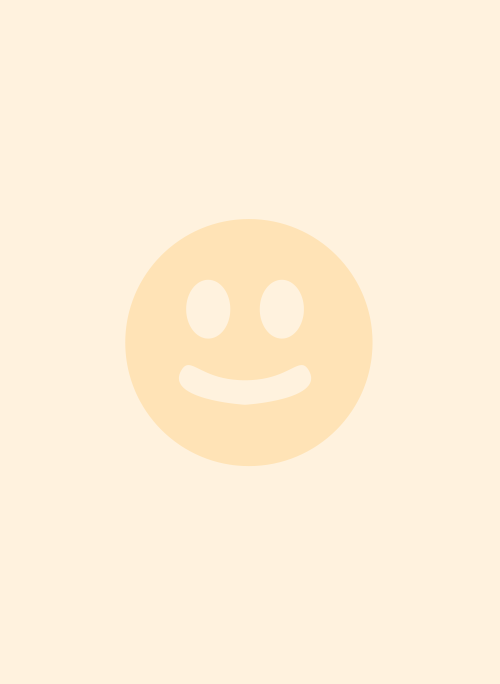それは僕がずっと気になって仕方ない事だった。
塩谷さんという人物を知れば知るほど、自分の子供を十八年間も放って置けるような人間には思えなかったからだ。
僕の言葉に塩谷さんは「そうだねえ」とのんびりした口調で考え込んだ。不躾な質問に気を悪くしたのか、とも思ったが、そうではないらしい。
「君はあの子の母親に会った事があるかい?」
僕は頭を振った。一度会ってみたいと思うものの、そんな機会には恵まれなかったのだ。
「そうか……。とても美しい人だったよ。今の雅巳を見ていると、出会った頃のあの人を思い出す。彼女は……僕より十も年上で、雅巳が出来たと分かった時、僕はまだ高校生だったんだ。親に、その事を話す勇気がなかった。学校を辞めて、彼女と共に突き進む勇気も・・・・・・。
彼女は、そんな僕の気持ちを敏感に感じ取って、何も言わずに、僕の前から消えた。当時の僕は、ホッとしてしまった。僕は愚かだったんだ。本当に大切なものが分からなかった」
塩谷さんは深い溜息をつき、哀愁漂う瞳を彷徨わせて、塩谷さんは言葉を続けた。
塩谷さんという人物を知れば知るほど、自分の子供を十八年間も放って置けるような人間には思えなかったからだ。
僕の言葉に塩谷さんは「そうだねえ」とのんびりした口調で考え込んだ。不躾な質問に気を悪くしたのか、とも思ったが、そうではないらしい。
「君はあの子の母親に会った事があるかい?」
僕は頭を振った。一度会ってみたいと思うものの、そんな機会には恵まれなかったのだ。
「そうか……。とても美しい人だったよ。今の雅巳を見ていると、出会った頃のあの人を思い出す。彼女は……僕より十も年上で、雅巳が出来たと分かった時、僕はまだ高校生だったんだ。親に、その事を話す勇気がなかった。学校を辞めて、彼女と共に突き進む勇気も・・・・・・。
彼女は、そんな僕の気持ちを敏感に感じ取って、何も言わずに、僕の前から消えた。当時の僕は、ホッとしてしまった。僕は愚かだったんだ。本当に大切なものが分からなかった」
塩谷さんは深い溜息をつき、哀愁漂う瞳を彷徨わせて、塩谷さんは言葉を続けた。