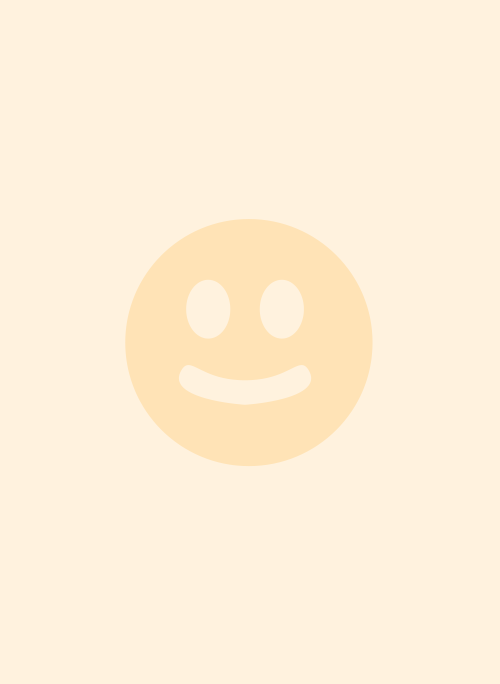普段、極力体を動かさないようにしていた雅巳が急に動いたことでいろいろな体の機能が麻痺を起こしたのだろう。
「誰か、須藤を保健管理センターに連れて行ってくれ」
僕は雅巳を抱いたまま立ち上がった。
「上田先生、俺が連れて行きます」
周囲の突き刺さる様な視線を感じながら僕は、そう言い放っていた。上田は安心したように「頼むよ」と俺に肩に手を置いた。俺はそれに対して軽く頷き、上田と半田に背中を向ける。僕は雅巳の体温を感じながら、保健管理センターに向かった。
腕の中の雅巳の体は僕が思っていた以上に、ずっと軽かった。
保健管理センターにはS大病院の医師がいて、簡単な治療や薬を出してくれるシステムになっている。そこで手におえない状態の場合はS大病院を紹介してもらえるよ
うになっているのだ。雅巳の場合はS大病院に定期検診に通っているほどだから、保健管理センターの医師がてこずるようだったら、すぐに病院の方に回されるようになっているのだろう。
まるで、それを意識してこの大学に入学したみたいだ。
そう思ってしまうのは僕だけだろうか?
保健管理センターには運がよく若い男の医師がいた。
「誰か、須藤を保健管理センターに連れて行ってくれ」
僕は雅巳を抱いたまま立ち上がった。
「上田先生、俺が連れて行きます」
周囲の突き刺さる様な視線を感じながら僕は、そう言い放っていた。上田は安心したように「頼むよ」と俺に肩に手を置いた。俺はそれに対して軽く頷き、上田と半田に背中を向ける。僕は雅巳の体温を感じながら、保健管理センターに向かった。
腕の中の雅巳の体は僕が思っていた以上に、ずっと軽かった。
保健管理センターにはS大病院の医師がいて、簡単な治療や薬を出してくれるシステムになっている。そこで手におえない状態の場合はS大病院を紹介してもらえるよ
うになっているのだ。雅巳の場合はS大病院に定期検診に通っているほどだから、保健管理センターの医師がてこずるようだったら、すぐに病院の方に回されるようになっているのだろう。
まるで、それを意識してこの大学に入学したみたいだ。
そう思ってしまうのは僕だけだろうか?
保健管理センターには運がよく若い男の医師がいた。