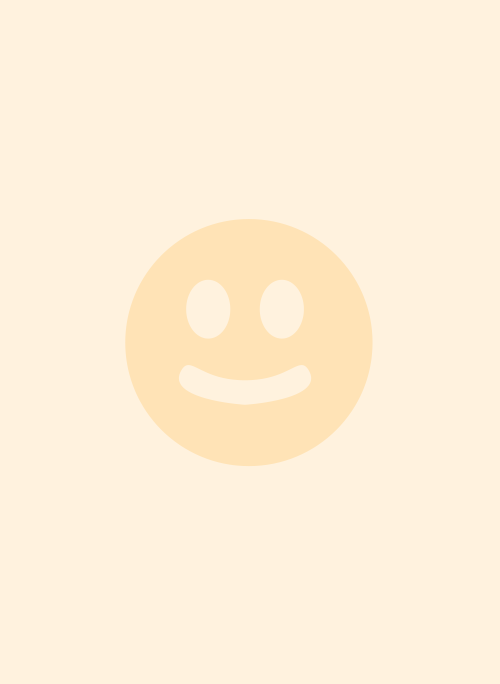でも、僕の胸騒ぎはそんな感情など流していく。
良枝が言っていたではないか。
雅巳は心臓が悪いんだと。
だから絶対に走ったりしないし、体育はいつも見学だったと。
それなのに、何でバトミントンをしているんだ。危険すぎる!
僕はバトミントンの羽を追いかける雅巳の元に歩き出していた。
巻き上がるブーイングの嵐を背に僕は雅巳の腕を掴んでいた。半田の非難するような視線が邪魔するな、と告げていた。
ポトリ、と音をたてて雅巳が追いかけていたバトミントンの羽が体育館の床に落ちた。
雅巳が夢から覚めたような表情で僕の顔を見つめた。
「加……藤?」
「何、無理しているんだ!」
怒りに任せて怒鳴っていた。体育館中が水を張ったように静まり返った。楽しく雅巳の試合を観戦していた男どもが邪魔された事への怒りを僕にぶつけていた。
雅巳の頬は紅潮していた。大きく目を見開き、驚いたように僕を見ている。
「どうして……?」
泣きそうな表情をしながら、雅巳の体から力が抜けていく。ズルズルと床に倒れるように、その場でしゃがみこみ、雅巳は僕の胸の中で意識を手放した。
「オイ!誰か先生を呼べ!」
良枝が言っていたではないか。
雅巳は心臓が悪いんだと。
だから絶対に走ったりしないし、体育はいつも見学だったと。
それなのに、何でバトミントンをしているんだ。危険すぎる!
僕はバトミントンの羽を追いかける雅巳の元に歩き出していた。
巻き上がるブーイングの嵐を背に僕は雅巳の腕を掴んでいた。半田の非難するような視線が邪魔するな、と告げていた。
ポトリ、と音をたてて雅巳が追いかけていたバトミントンの羽が体育館の床に落ちた。
雅巳が夢から覚めたような表情で僕の顔を見つめた。
「加……藤?」
「何、無理しているんだ!」
怒りに任せて怒鳴っていた。体育館中が水を張ったように静まり返った。楽しく雅巳の試合を観戦していた男どもが邪魔された事への怒りを僕にぶつけていた。
雅巳の頬は紅潮していた。大きく目を見開き、驚いたように僕を見ている。
「どうして……?」
泣きそうな表情をしながら、雅巳の体から力が抜けていく。ズルズルと床に倒れるように、その場でしゃがみこみ、雅巳は僕の胸の中で意識を手放した。
「オイ!誰か先生を呼べ!」