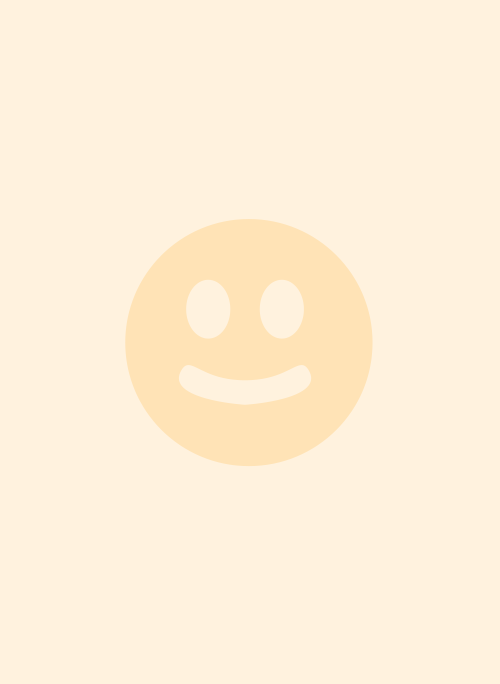しかし、そんな事より僕を憂鬱にさせる事があった。
雅巳と同じ班には、雅巳の事を狙っている半田俊哉がいた事だ。
俊哉が雅巳の事を見る目は、あからさま過ぎる。僕に対して敵意剥き出しな態度も、正直言って気に入らなかった。
「オイ、加藤」
授業が始まる前、半田に声をかけられて、僕はイヤイヤながらも、顔だけ半田の方に向けた。
「何だよ」
「最近、お前さ、須藤さんと一緒にいる事が多いよな。付き合っているのか?」
半田の言葉に僕はすごく嫌な顔をしてしまったようだ。半田は答えを聞く前に、僕の表情を見た事で答えを見つけてしまったようだ。
「何だ。付き合っているわけじゃないんだな」
勝ち誇ったような半田の表情に、ムカついてしょうがない。
「それじゃ、俺とお前は同じ立場だと思っていいわけだな。ま、お互い頑張ろうや」
半田は僕に何も言わせず、言いたい事だけ言って僕の肩を叩いて去って行った。
何だよ、アイツ。
勝手に話し掛けてきて人が何か言う前に自己完結していった。
あんな中身がないヤツを雅巳が選ぶはずがない。
負け惜しみのようにそんな事を思いながら、僕はバトミントンの授業が行われている総合体育館に向かった。
雅巳と同じ班には、雅巳の事を狙っている半田俊哉がいた事だ。
俊哉が雅巳の事を見る目は、あからさま過ぎる。僕に対して敵意剥き出しな態度も、正直言って気に入らなかった。
「オイ、加藤」
授業が始まる前、半田に声をかけられて、僕はイヤイヤながらも、顔だけ半田の方に向けた。
「何だよ」
「最近、お前さ、須藤さんと一緒にいる事が多いよな。付き合っているのか?」
半田の言葉に僕はすごく嫌な顔をしてしまったようだ。半田は答えを聞く前に、僕の表情を見た事で答えを見つけてしまったようだ。
「何だ。付き合っているわけじゃないんだな」
勝ち誇ったような半田の表情に、ムカついてしょうがない。
「それじゃ、俺とお前は同じ立場だと思っていいわけだな。ま、お互い頑張ろうや」
半田は僕に何も言わせず、言いたい事だけ言って僕の肩を叩いて去って行った。
何だよ、アイツ。
勝手に話し掛けてきて人が何か言う前に自己完結していった。
あんな中身がないヤツを雅巳が選ぶはずがない。
負け惜しみのようにそんな事を思いながら、僕はバトミントンの授業が行われている総合体育館に向かった。