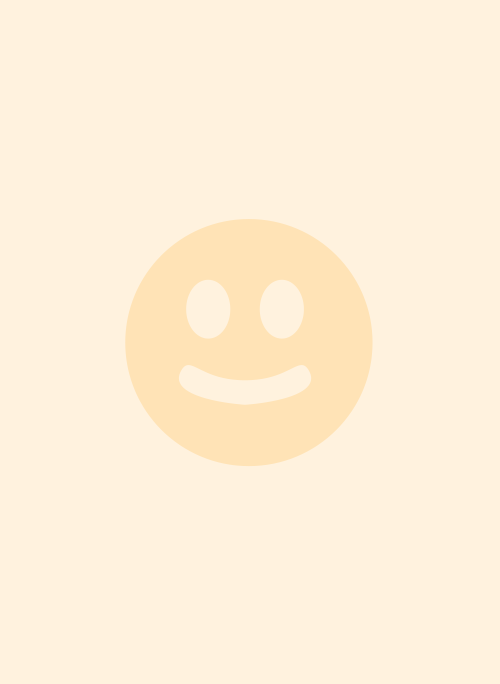ただ、どんなに親しく振舞っていても決して自分から相手に何かを求めることはないのだ。
気が付くと、雅巳の視線が良枝を追っている。良枝にしてもそれは同じだ。それなのに、二人は互いに声をかけ合うことはなく、すれ違うだけだ。雅巳と違い、不器用な良枝は一人でいることが多かった。それを雅巳は気にしているようだった。
しかし、孤立していても、良枝は寂しいと思っていないようだ。もしかすると、良枝は僕が思っている以上に気が強い女の子なのかもしれない。
そんな良枝と雅巳の間に何があったのだろう?
気にはなっていたが、その事に立ち入るのを雅巳は許さないだろう。雅巳に嫌われたくない僕は、遠巻きに二人の様子を見守る事しか出来なかった。
もちろん、そんな状態で、雅巳と話し合いなど出来るはずもない。雅巳も僕と二人っきりになろうとはしなかった。
あくまでも友達。それ以上はない。
彼女は自ら言っていた通りの関係と割り切って、僕に接している。そして、僕もその関係を崩すことが出来ないまま、時間だけが過ぎていってしまっていた。
僕は、雅巳に嫌われるのが怖かった。臆病だったのだ。
気が付くと、雅巳の視線が良枝を追っている。良枝にしてもそれは同じだ。それなのに、二人は互いに声をかけ合うことはなく、すれ違うだけだ。雅巳と違い、不器用な良枝は一人でいることが多かった。それを雅巳は気にしているようだった。
しかし、孤立していても、良枝は寂しいと思っていないようだ。もしかすると、良枝は僕が思っている以上に気が強い女の子なのかもしれない。
そんな良枝と雅巳の間に何があったのだろう?
気にはなっていたが、その事に立ち入るのを雅巳は許さないだろう。雅巳に嫌われたくない僕は、遠巻きに二人の様子を見守る事しか出来なかった。
もちろん、そんな状態で、雅巳と話し合いなど出来るはずもない。雅巳も僕と二人っきりになろうとはしなかった。
あくまでも友達。それ以上はない。
彼女は自ら言っていた通りの関係と割り切って、僕に接している。そして、僕もその関係を崩すことが出来ないまま、時間だけが過ぎていってしまっていた。
僕は、雅巳に嫌われるのが怖かった。臆病だったのだ。