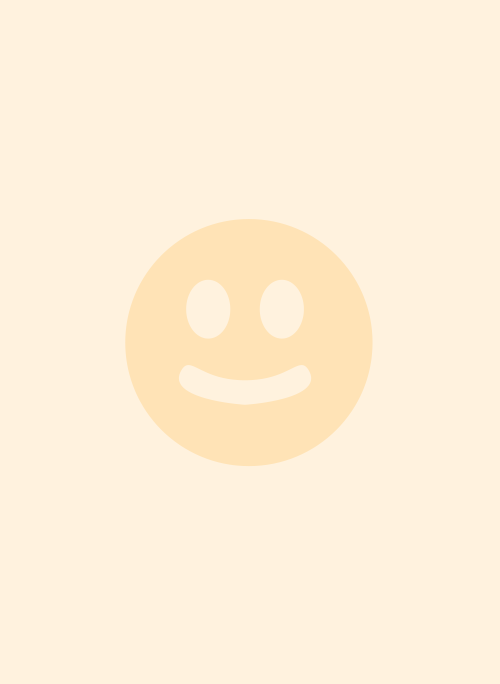でもそれが恋してはいけない理由になるだろうか?
雅巳に幸せになって欲しい。
そう思うのに、加藤君と雅巳が一緒にいる未来は見たくなかった。
これは親友を取られてしまうことの寂しさなのだろうか?
それとも……もっと別の感情なのだろうか?
私には、その感情が何なのか、よく分からないでいた。
「良枝、顔色が悪いわよ。どうかした?」
雅巳の顔が私の方を覗き込んでいる。
いつものように、一緒に帰る大学から家までの帰り道。
口を固く結んで一言も言葉を発しようとしない私の事を、雅巳は本当に心配してくれているのだろう。普段の私は雅巳といると自然に口数が多かったから余計に心配になったに違いないのだ。
私は雅巳の言葉には反応せず、自分の足もとのアスファルトに視線を落としたまま、暗い気持ちを抱えていた。
「最近、ボーとしていることが多いし、何かあったの?」
雅巳は私を心配してくれている。それは分かっているが、それが今は、とても重たく感じる。それどころか放っておいて欲しいと思ってしまうのは何故だろう?
今まで私は、雅巳の事をそんな風に思った事はない。
「良枝、熱でもあるの?」
雅巳に幸せになって欲しい。
そう思うのに、加藤君と雅巳が一緒にいる未来は見たくなかった。
これは親友を取られてしまうことの寂しさなのだろうか?
それとも……もっと別の感情なのだろうか?
私には、その感情が何なのか、よく分からないでいた。
「良枝、顔色が悪いわよ。どうかした?」
雅巳の顔が私の方を覗き込んでいる。
いつものように、一緒に帰る大学から家までの帰り道。
口を固く結んで一言も言葉を発しようとしない私の事を、雅巳は本当に心配してくれているのだろう。普段の私は雅巳といると自然に口数が多かったから余計に心配になったに違いないのだ。
私は雅巳の言葉には反応せず、自分の足もとのアスファルトに視線を落としたまま、暗い気持ちを抱えていた。
「最近、ボーとしていることが多いし、何かあったの?」
雅巳は私を心配してくれている。それは分かっているが、それが今は、とても重たく感じる。それどころか放っておいて欲しいと思ってしまうのは何故だろう?
今まで私は、雅巳の事をそんな風に思った事はない。
「良枝、熱でもあるの?」