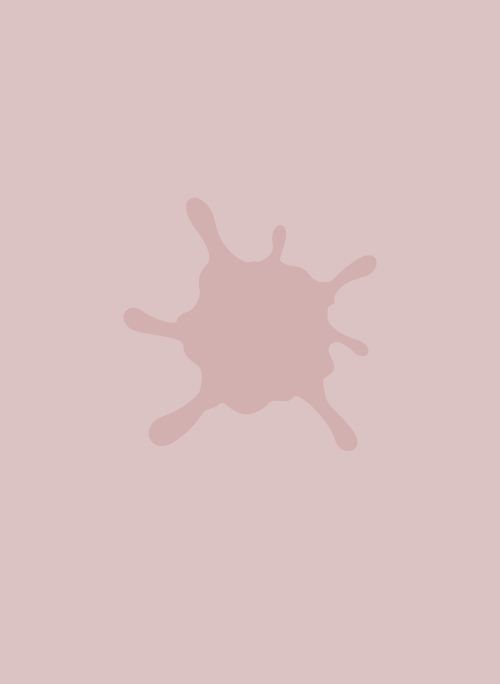やば…泣きそう。
そう思ったときにはもう遅くて…
「ッ」
私は、涙を流してしまった。
「な、奈留ちゃん…」
先生が心配そうに顔を覗き込んできた。
「っ…大丈夫…です…すいません…っ」
「………じゃあ先生は戻るね。あ、みなさんも…」
「…あ、はい…」
お母さんとお父さんは、先生と一緒に部屋を出ようとした。
だけど、翔は部屋を出ようとはしなかった。
「…君にも話があるんだ。悪いけれど、一緒に来てくれるかい?」
でも翔は顔を歪ませながら言う。
「…俺…奈留のそばを離れたくないんです。そばにいたいんです…」
翔…
「ごめんね。翔君…だっけ?本当に、話しとかないといけないんだ」
翔は少し黙り込んで…
「…はい。分かりました」
ガララ
みんな出て行った。
一人でいる病室は、本当に、本当に静かだった。
もう…真夜中だもんな。
そりゃあそうか…
“病気”だって言われたのに、こんなこと考えてるなんて、変な感じだ。
…まだ…全然…実感が…ないんだよ…
死ぬかもしれないなんて、信じられないんだよ…
そう思ったときにはもう遅くて…
「ッ」
私は、涙を流してしまった。
「な、奈留ちゃん…」
先生が心配そうに顔を覗き込んできた。
「っ…大丈夫…です…すいません…っ」
「………じゃあ先生は戻るね。あ、みなさんも…」
「…あ、はい…」
お母さんとお父さんは、先生と一緒に部屋を出ようとした。
だけど、翔は部屋を出ようとはしなかった。
「…君にも話があるんだ。悪いけれど、一緒に来てくれるかい?」
でも翔は顔を歪ませながら言う。
「…俺…奈留のそばを離れたくないんです。そばにいたいんです…」
翔…
「ごめんね。翔君…だっけ?本当に、話しとかないといけないんだ」
翔は少し黙り込んで…
「…はい。分かりました」
ガララ
みんな出て行った。
一人でいる病室は、本当に、本当に静かだった。
もう…真夜中だもんな。
そりゃあそうか…
“病気”だって言われたのに、こんなこと考えてるなんて、変な感じだ。
…まだ…全然…実感が…ないんだよ…
死ぬかもしれないなんて、信じられないんだよ…
 | 野いちご](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.784/img/logo.svg)