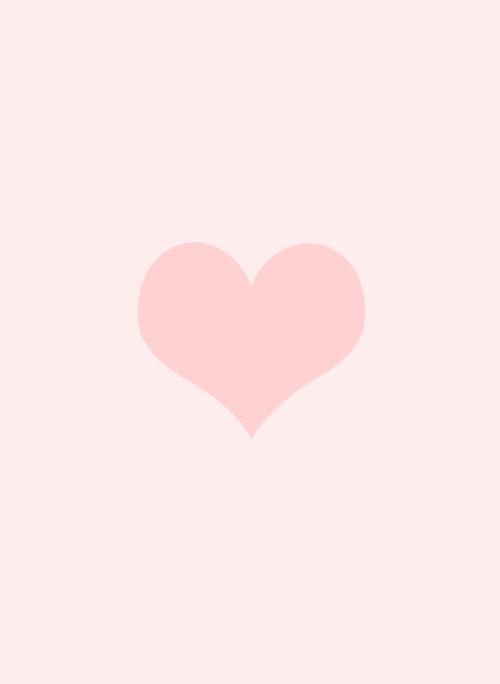第二章・殺意
イシュタルパレスで最も大きな白夜の間では、夕食を兼ねた舞踏会が開かれていた。
広間の一番奥まった、数段高くしつらえられた場所に、玉座の肘掛けにややだらしなくもたれる様にして卑弥呼は座した。一国の君主としてはお世辞にも褒められたお行儀ではなかったが、それが余計に彼女を妖しく艶めかしく人々に見せている。彼女は美しかった。
卑弥呼は鬼道なる人知を超えた力を操る、と言われている。現代の科学社会において、それはカルト宗教のまやかしとして他国では理解されていた。が、
(案外、超常のちからというのもまるっきり嘘ではないのかもしれない・・・即位から30年以上はたっている。本来はもういい年齢のはずだ。しかしあの姿・・・20代後半か、いっても30代にしか見えない)
と、相田はワインの注がれたグラスを傾けながら、横目で生ける伝説的人物を盗み見た。
イシュタルパレスで最も大きな白夜の間では、夕食を兼ねた舞踏会が開かれていた。
広間の一番奥まった、数段高くしつらえられた場所に、玉座の肘掛けにややだらしなくもたれる様にして卑弥呼は座した。一国の君主としてはお世辞にも褒められたお行儀ではなかったが、それが余計に彼女を妖しく艶めかしく人々に見せている。彼女は美しかった。
卑弥呼は鬼道なる人知を超えた力を操る、と言われている。現代の科学社会において、それはカルト宗教のまやかしとして他国では理解されていた。が、
(案外、超常のちからというのもまるっきり嘘ではないのかもしれない・・・即位から30年以上はたっている。本来はもういい年齢のはずだ。しかしあの姿・・・20代後半か、いっても30代にしか見えない)
と、相田はワインの注がれたグラスを傾けながら、横目で生ける伝説的人物を盗み見た。