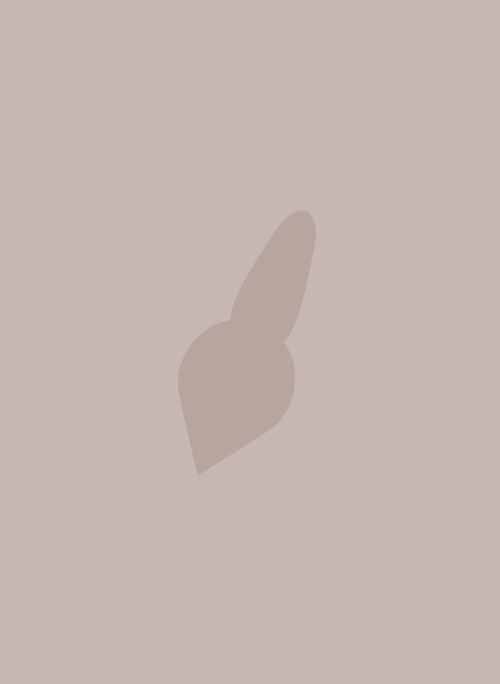「兼山、面会だ。」
厳しい口調で警官が言う。
「樹里…。」
彼はやつれた表情で中野樹里を見つめた。そして彼女はニッコリと笑いかけ、礼をした。
「東。久しぶりだね。」
「ああ。よく来たな。」
二人はたわいもない挨拶をしたあと、樹里が彼の最も気になっていることを切り出した。
「先生、大丈夫だよ。きっと東の帰りをずっと待ってるよ。」
「…そっか。そうだといいな。」
彼の顔がほころんだ。外は赤々と太陽が燃えていた。
苦しい…吐きたい。命を生むということはこんなに辛いことなんだと私は痛いほど感じていた。まるで私と彼の恋愛のように。
―ピンポーン―
誰かがチャイムを鳴らした。私は壁をつたいながら玄関のドアを開けた。
「先生!?どうしたの、顔が真っ青だよ。」
中野樹里が心配そうに顔をのぞきこむ。
「…う、うん。大丈夫よ。ちょっと疲れが出て、体調を崩しただけ…うっ…。」
胃からのどへ気持ち悪いものが一気に押し寄せてくる。私は彼女をほったらかしにして急いで洗面所へ駆け込んだ。
「先生、もしかして、ひ、東の子ども…。」
鏡越しに彼女の姿が映っている。私は覚悟を決めて話さなければと思っていた。
「そう、医者へ行ったの。」
彼女は落ち着いて聞いてくれた。
「東には何て言うの?」
「…わからない。まだ産むって決めたわけじゃないもの。」
厳しい口調で警官が言う。
「樹里…。」
彼はやつれた表情で中野樹里を見つめた。そして彼女はニッコリと笑いかけ、礼をした。
「東。久しぶりだね。」
「ああ。よく来たな。」
二人はたわいもない挨拶をしたあと、樹里が彼の最も気になっていることを切り出した。
「先生、大丈夫だよ。きっと東の帰りをずっと待ってるよ。」
「…そっか。そうだといいな。」
彼の顔がほころんだ。外は赤々と太陽が燃えていた。
苦しい…吐きたい。命を生むということはこんなに辛いことなんだと私は痛いほど感じていた。まるで私と彼の恋愛のように。
―ピンポーン―
誰かがチャイムを鳴らした。私は壁をつたいながら玄関のドアを開けた。
「先生!?どうしたの、顔が真っ青だよ。」
中野樹里が心配そうに顔をのぞきこむ。
「…う、うん。大丈夫よ。ちょっと疲れが出て、体調を崩しただけ…うっ…。」
胃からのどへ気持ち悪いものが一気に押し寄せてくる。私は彼女をほったらかしにして急いで洗面所へ駆け込んだ。
「先生、もしかして、ひ、東の子ども…。」
鏡越しに彼女の姿が映っている。私は覚悟を決めて話さなければと思っていた。
「そう、医者へ行ったの。」
彼女は落ち着いて聞いてくれた。
「東には何て言うの?」
「…わからない。まだ産むって決めたわけじゃないもの。」