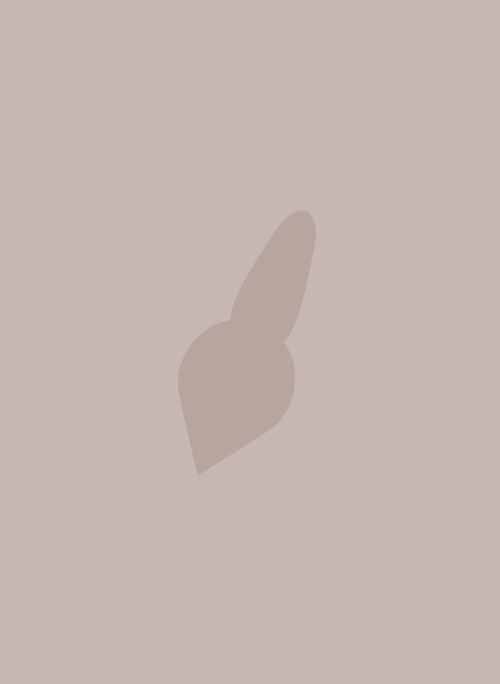声は段々と弱弱しくなり、切ないほど彼女の感情が彼の胸に突き刺さる。
「樹里…。そんなに俺のことを思ってくれてるなんて知らなかった。でも、本当にゴメン。樹里が俺のことを思ってくれてるのと同じくらい俺も先生のことを好きなんだ。だから樹里のことは愛してあげられない。」
沈黙は続く。中野樹里の肩が震えていることに彼は気づいた。そしてそっと肩に手を置くと彼は顔を近づけて中野樹里の唇に自分の口を押し当てた。彼女はこれ以上にない驚きの顔で目を丸くし、何が起こったか理解できずにいた。
「樹里。愛している。いつか結婚しよう。」
そう言って彼は彼女のことを強く抱きしめた。
「ひ、ひがし…?」
しばらく抱き合った後、彼は自分の体を離した。
「これが先生と会う前の俺の正直な気持ちだ。」
彼はニッコリと笑い彼女を見つめた。
目覚めると彼の姿はなかった。私は夢を見ていたのだろうか。まだあの根岸先生の家に監禁されてるのではないだろうか。いやだ、もうあの場所には戻りたくない。私は次の瞬間手を動かすと微かにメモ紙をつかんでいた。
「これは、彼の書いた詩…。」
夢じゃなかった。彼は確かにここにいて私を愛してくれた…。けれど私はどうしようもなく孤独感を抱いていた。
薄暗い病院の中を無情な足音が鳴り響く。そしてある病室の前でその足音は止まった。
「来る頃だとは思っていたよ、兼山君。」
薄明りにぼんやり光る不吉な顔。根岸千尋はニヤッと笑い彼を出迎えた。
「出迎え、わざわざどうも。」
心無い言葉で彼は目を伏せた形の礼をした。
「いやあ。先日は置き土産をどうも、ここのね。」
「樹里…。そんなに俺のことを思ってくれてるなんて知らなかった。でも、本当にゴメン。樹里が俺のことを思ってくれてるのと同じくらい俺も先生のことを好きなんだ。だから樹里のことは愛してあげられない。」
沈黙は続く。中野樹里の肩が震えていることに彼は気づいた。そしてそっと肩に手を置くと彼は顔を近づけて中野樹里の唇に自分の口を押し当てた。彼女はこれ以上にない驚きの顔で目を丸くし、何が起こったか理解できずにいた。
「樹里。愛している。いつか結婚しよう。」
そう言って彼は彼女のことを強く抱きしめた。
「ひ、ひがし…?」
しばらく抱き合った後、彼は自分の体を離した。
「これが先生と会う前の俺の正直な気持ちだ。」
彼はニッコリと笑い彼女を見つめた。
目覚めると彼の姿はなかった。私は夢を見ていたのだろうか。まだあの根岸先生の家に監禁されてるのではないだろうか。いやだ、もうあの場所には戻りたくない。私は次の瞬間手を動かすと微かにメモ紙をつかんでいた。
「これは、彼の書いた詩…。」
夢じゃなかった。彼は確かにここにいて私を愛してくれた…。けれど私はどうしようもなく孤独感を抱いていた。
薄暗い病院の中を無情な足音が鳴り響く。そしてある病室の前でその足音は止まった。
「来る頃だとは思っていたよ、兼山君。」
薄明りにぼんやり光る不吉な顔。根岸千尋はニヤッと笑い彼を出迎えた。
「出迎え、わざわざどうも。」
心無い言葉で彼は目を伏せた形の礼をした。
「いやあ。先日は置き土産をどうも、ここのね。」