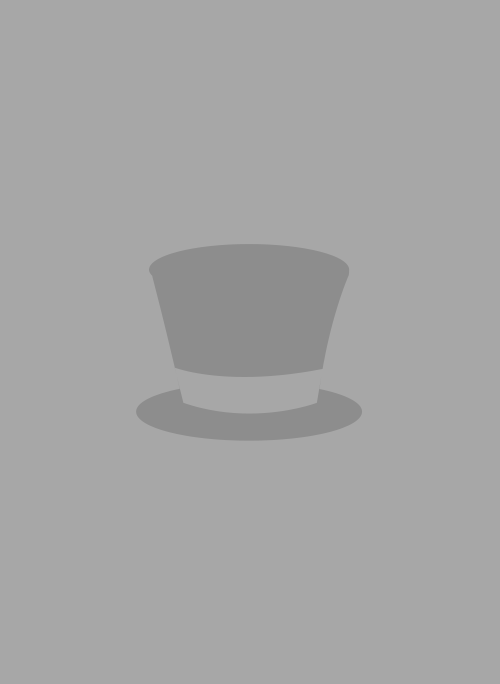「ほら、降りろ」
「い~や~!」
あたしはシートベルトにしがみ付き、首を横に振る。
そんなあたしにハァと圭くんの溜息が聞こえた。
「馬鹿。何もしねぇよ。
ただ、図書館は他の奴の目もあるから、教えるのも教えづらいから俺の部屋にしただけだ。
変なこと考えてんな」
軽く頭をコツンと叩かれる。
あたしは叩かれた場所を触りながら、圭くんのことを見た。
「本当?」
圭くんはフッと視線を逸らすと、「本当だ」と呟く。
どうしてそこで目を逸らす?
「本当に本当?」
「ああ…」
「じゃあ、どうして目を逸らすの?
本当は後ろめたいことを考えてたり…」
「してねぇよ!」
「じゃあ!」
「うるせぇ!
とにかく、何もしないからさっさと降りろ」
まだ、完全に圭くんのことを信じたわけではないけど、さすがの圭くんも親同士が仲がいいあたしに下手なことはしないだろうという打算的な考えにより、あたしは車から降りた。