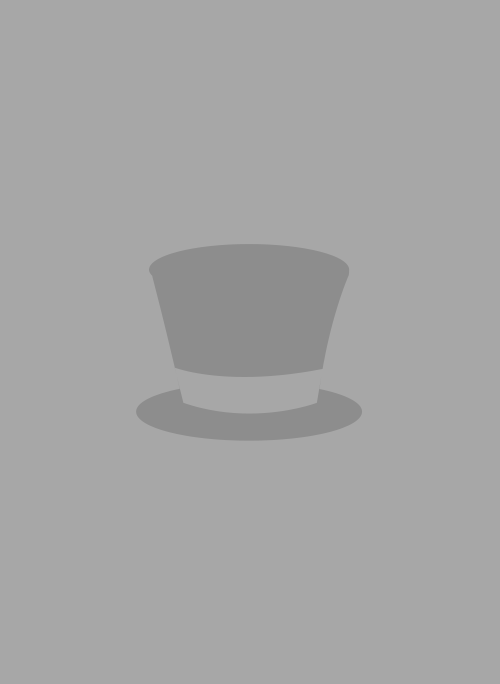「お、降ろして!」
「なんだよ、急に」
「いいから、降ろして!
あたし、聞いてない!
圭くんの家に行くなんて聞いてない!」
「そりゃそうだろ。
俺、言った覚えないもん」
もんって、もんって可愛く言っても、全然可愛くなんてないんだから!
「圭くん、家に連れ込んで、あたしをどうするつもり!?」
「はぁ!? どうって……」
運よく?
信号が赤に変わり、あたしのことを見てきた圭くんは一瞬驚いたような顔をしながらも、ニヤリと笑う。
「さ~て、どう料理しようかな~?」
ひぇ~~~!
あたし、このままじゃ、圭くんにやられちゃうよ~!
だって、圭くんは一夜の恋を楽しむような遊び人。そんな手が早い人間なんだもん。
好意を持たれているってことだし、もしかしたら、あたし―――…
「あたしなんかを料理しちゃっても、全然美味しくなんてないんだから!」
「それは、食ってみないとわからないだろ?」
「わかります、わかります!
いつも圭くん言ってるじゃない。
あたしのこと子供だって。
子供のあたしなんて食べても全然美味しくなんてないんだよ。
ほら、言うじゃない。
青いものよりもよく熟れたもののほうが果物でも美味しいでしょ!?」
「お前、何の話してんの?」
呆れた風に見られても、全然構わない。
こっちとしては、必死なんだから!
だけど、あたしの必死な説得もむなしく、車は圭くんが一人暮らしをしているアパートへと着いたのだった。