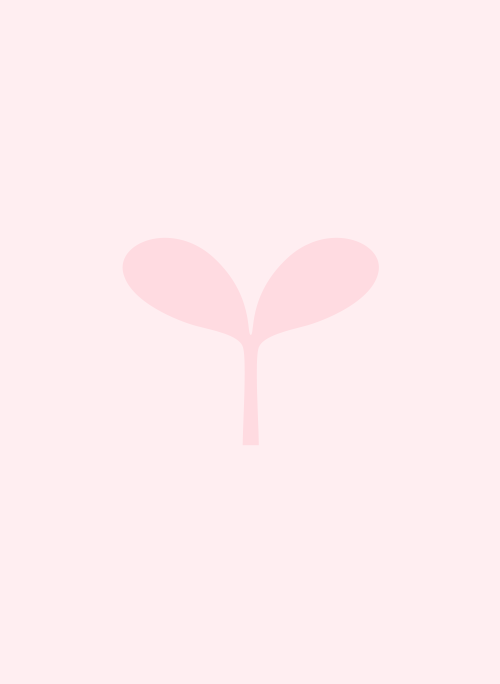そんな遊水の様子が唯一違って見えたのは──円士郎に関する話をした時だった。
共通の友人であるわけだから当然、生き物や蘭学の話に加えて、円士郎の話題は遊水との会話でしばしば私たちの口に上った。
何より、あの奇想天外破天荒な御曹司のことについてついて話すのは
──私にとっては楽しかったのだ。
それが何を意味するのか
私が認識するのはまだ先のことだったが。
冬の間は暇だからと言って、金魚が死んでしまってからも遊水は私の長屋に入り浸っていて、
遊水や円士郎と出会って初めての年が明けて、冬の寒さも遠退いた二月のその日も、円士郎の話で盛り上がっていたら──
ふと、遊水の表情が曇った。
「亜鳥はいつも、随分生き生きと円士郎様のことを話すんだな」
じっと私の顔を窺いながら、遊水はそんなことを言った。
「……まあ、面白い奴だからな」
「違いねえ」
私の言葉にそう返したきり、遊水は黙り込んでしまった。
ひょっとして……
どこか沈み込んだ彼の様子を見て、私は淡い期待を抱いた。
これはヤキモチを焼いてくれているのだろうか。
いやいやまさか、と
すぐに馬鹿馬鹿しい考えを振り払う。
円士郎より遙かに女遊びに通じた遊水が、嫉妬などするとは思えない。
そもそも、未だ何一つ手出しされていないこの状況で、彼が私に思いを寄せてくれているかどうかすらも怪しい。
なんて思っていたら──
「嫉妬するねェ」
どこか諦観に似た苦笑を浮かべて遊水がそう言ったので、私はびっくりした。
不覚にもまたまた胸が高鳴ったりして
「円士郎様のようなお人なら──本気で惚れた女も幸せにできるんだろうな。
……この俺とは違ってね」
どうやら嫉妬の意味が違っていた。
共通の友人であるわけだから当然、生き物や蘭学の話に加えて、円士郎の話題は遊水との会話でしばしば私たちの口に上った。
何より、あの奇想天外破天荒な御曹司のことについてついて話すのは
──私にとっては楽しかったのだ。
それが何を意味するのか
私が認識するのはまだ先のことだったが。
冬の間は暇だからと言って、金魚が死んでしまってからも遊水は私の長屋に入り浸っていて、
遊水や円士郎と出会って初めての年が明けて、冬の寒さも遠退いた二月のその日も、円士郎の話で盛り上がっていたら──
ふと、遊水の表情が曇った。
「亜鳥はいつも、随分生き生きと円士郎様のことを話すんだな」
じっと私の顔を窺いながら、遊水はそんなことを言った。
「……まあ、面白い奴だからな」
「違いねえ」
私の言葉にそう返したきり、遊水は黙り込んでしまった。
ひょっとして……
どこか沈み込んだ彼の様子を見て、私は淡い期待を抱いた。
これはヤキモチを焼いてくれているのだろうか。
いやいやまさか、と
すぐに馬鹿馬鹿しい考えを振り払う。
円士郎より遙かに女遊びに通じた遊水が、嫉妬などするとは思えない。
そもそも、未だ何一つ手出しされていないこの状況で、彼が私に思いを寄せてくれているかどうかすらも怪しい。
なんて思っていたら──
「嫉妬するねェ」
どこか諦観に似た苦笑を浮かべて遊水がそう言ったので、私はびっくりした。
不覚にもまたまた胸が高鳴ったりして
「円士郎様のようなお人なら──本気で惚れた女も幸せにできるんだろうな。
……この俺とは違ってね」
どうやら嫉妬の意味が違っていた。