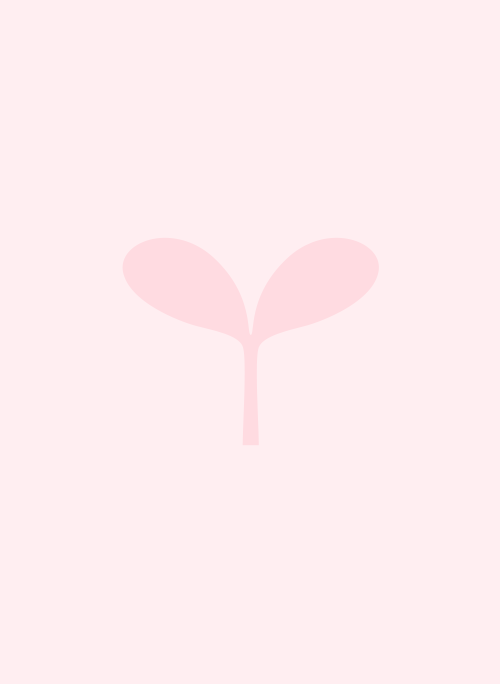季節は移ろい、秋が過ぎ冬が訪れようとしていた頃。
突然、金魚が死んだ。
まずランチュウ二匹が死に、続いて残りの四匹の元気がなくなって、
遊水から、調子が悪い時は塩を入れると良いと聞いていたのでそれも試したが、結局持ち直すことはなく、赤い儚い魚たちはばたばたと全滅してしまった。
「急に冷えてきたからな」
遊水は、綺麗な翠色の瞳に死んだ金魚を映してそう呟いて、
意気消沈している私に、この季節に金魚の調子が崩れることは多いのだと言った。
「代わりを持って来ようか」
優しい声音で紡がれた言葉に、私は頭を殴られたような気がした。
代わり。
「残酷なことを言うのだな」
土間に立つ遊水の顔を板の間に座ったまま睨み上げ、彼の顔に私を気遣う表情が浮かんでいるのに気づいて──泣きたくなった。
悪気があって放たれたセリフではないのだろう。
不注意で死なせてしまった魚の代わりを勧めるなど、金魚屋の彼とて不本意なのかもしれないし、落ち込んでいる私を慰めようとして口にしたのだろうと思われた。
けれど。
死んだ赤い魚を前にして、あっさりと「代わり」なんて言われたら──
このかわいそうな魚たちも、金魚屋のもとには「代わり」がたくさんいるのだとほのめかされたら──
連想してしまう。
遊び慣れた彼にとっては、女もまたこの魚と同じなのではないか。
私がいなくなっても、他にも代わりの女ならいくらでもいるということなのではないか。
突然、金魚が死んだ。
まずランチュウ二匹が死に、続いて残りの四匹の元気がなくなって、
遊水から、調子が悪い時は塩を入れると良いと聞いていたのでそれも試したが、結局持ち直すことはなく、赤い儚い魚たちはばたばたと全滅してしまった。
「急に冷えてきたからな」
遊水は、綺麗な翠色の瞳に死んだ金魚を映してそう呟いて、
意気消沈している私に、この季節に金魚の調子が崩れることは多いのだと言った。
「代わりを持って来ようか」
優しい声音で紡がれた言葉に、私は頭を殴られたような気がした。
代わり。
「残酷なことを言うのだな」
土間に立つ遊水の顔を板の間に座ったまま睨み上げ、彼の顔に私を気遣う表情が浮かんでいるのに気づいて──泣きたくなった。
悪気があって放たれたセリフではないのだろう。
不注意で死なせてしまった魚の代わりを勧めるなど、金魚屋の彼とて不本意なのかもしれないし、落ち込んでいる私を慰めようとして口にしたのだろうと思われた。
けれど。
死んだ赤い魚を前にして、あっさりと「代わり」なんて言われたら──
このかわいそうな魚たちも、金魚屋のもとには「代わり」がたくさんいるのだとほのめかされたら──
連想してしまう。
遊び慣れた彼にとっては、女もまたこの魚と同じなのではないか。
私がいなくなっても、他にも代わりの女ならいくらでもいるということなのではないか。