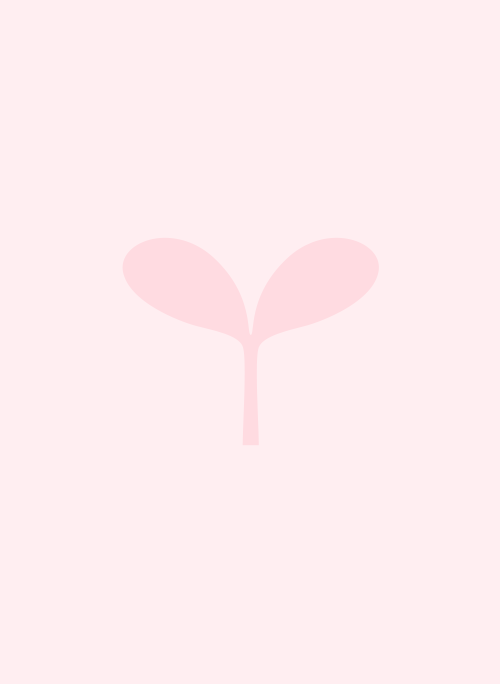それから、彼は三日と間を空けずに私の長屋を訪ねて来るようになり、私たちは様々な話をした。
金魚の話、
生き物の話、
彼が仕事で行ってきたという江戸の話、
蘭学の話……。
金魚の盆栽にはやはりそれなりに学問も必要ということなのか、驚いたことに蘭学や本草学についても私と遊水は、円士郎との会話とほとんど変わらない内容でもって言葉を交わした。
しかし彼がどこに店を構えているのか、どこで金魚の盆栽を行っているのか、それが話題に上ることはなく、私たちは最初に引いた互いの境界線を守り続けた。
そのことは、私に一抹の不安を残した。
こちらも時々長屋を訪れる円士郎にも聞けば、円士郎もまた、遊水がどこの何者であるのか、どこを住処としているのか、素性を知らないということだった。
つまり──
彼はこのように私に会いに来てくれているが、もしもその足が遠退いてしまった時──
円士郎の前からも彼が姿を消してしまった場合──
私のほうから彼を訪ねて行く方法は皆無なのだ。
そんな恐怖を抱えたまま、いつの間にか季節は真夏になり、
ある日、遊水はいいものをやると言って、びいどろで作られた丸い玉を持ってきた。
ちょうど風鈴を逆さまにしたようなもので、中には水を入れて紐で吊すことができるようになっていた。
「こいつは金魚玉というものでね」
と、彼は言った。
「金魚玉?」
首を傾げる私の前で、遊水は私がタライで飼っている金魚を一匹すくって、そのびいどろの玉の中に入れ、長屋の入り口の脇にある窓辺に吊した。
「こうして、金魚を入れて下から眺めて楽しめる。夏にはいいだろう」
なるほど、宙に浮いた透明な水玉の中で、赤い魚がキラキラとヒレをひるがえす様は何とも涼しげで、目から暑気払いをしてくれそうな気がした。
「しかし、こんなに狭い場所で少ない水の中に入れておいて、金魚は大丈夫なのかね?」
私はその、金魚一匹が何とか体の向きを変えることが可能なほどの、小さなびいどろの容器を見上げて心配になった。
金魚の話、
生き物の話、
彼が仕事で行ってきたという江戸の話、
蘭学の話……。
金魚の盆栽にはやはりそれなりに学問も必要ということなのか、驚いたことに蘭学や本草学についても私と遊水は、円士郎との会話とほとんど変わらない内容でもって言葉を交わした。
しかし彼がどこに店を構えているのか、どこで金魚の盆栽を行っているのか、それが話題に上ることはなく、私たちは最初に引いた互いの境界線を守り続けた。
そのことは、私に一抹の不安を残した。
こちらも時々長屋を訪れる円士郎にも聞けば、円士郎もまた、遊水がどこの何者であるのか、どこを住処としているのか、素性を知らないということだった。
つまり──
彼はこのように私に会いに来てくれているが、もしもその足が遠退いてしまった時──
円士郎の前からも彼が姿を消してしまった場合──
私のほうから彼を訪ねて行く方法は皆無なのだ。
そんな恐怖を抱えたまま、いつの間にか季節は真夏になり、
ある日、遊水はいいものをやると言って、びいどろで作られた丸い玉を持ってきた。
ちょうど風鈴を逆さまにしたようなもので、中には水を入れて紐で吊すことができるようになっていた。
「こいつは金魚玉というものでね」
と、彼は言った。
「金魚玉?」
首を傾げる私の前で、遊水は私がタライで飼っている金魚を一匹すくって、そのびいどろの玉の中に入れ、長屋の入り口の脇にある窓辺に吊した。
「こうして、金魚を入れて下から眺めて楽しめる。夏にはいいだろう」
なるほど、宙に浮いた透明な水玉の中で、赤い魚がキラキラとヒレをひるがえす様は何とも涼しげで、目から暑気払いをしてくれそうな気がした。
「しかし、こんなに狭い場所で少ない水の中に入れておいて、金魚は大丈夫なのかね?」
私はその、金魚一匹が何とか体の向きを変えることが可能なほどの、小さなびいどろの容器を見上げて心配になった。