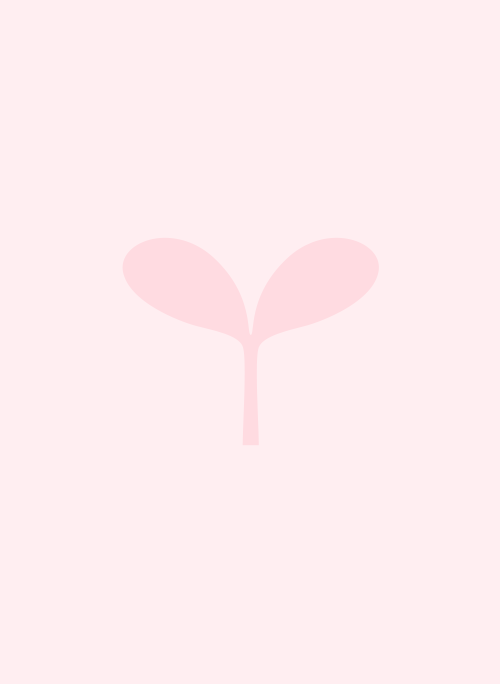黒い被り手拭いから覗く金の髪の下で、細められた緑の目が男たちを見据えていた。
思いがけない再会に驚くと同時に──私は、彼をこんな場面に巻き込んでしまったことに背筋が冷たくなったのだが、
「げ!? 遊水かよ」
この金髪の美青年を目にした途端、チンピラたちは青くなった。
知り合いらしく、名前までズバリ合っていた。
「てめえら、見たところ銀治郎親分さんところの若い奴らだな。この女は俺の恩人なんだが、どうかしたかい?」
「うえっ!? い、いや……」
「話をつける必要があるんなら、俺が親分さんのとこに行くぜ? 案内しな」
遊水の白い顔に貼りついた冷ややかな笑いや、チンピラたちに向けた刃物のような目つきは──そこらの町人や優男とは一線を画する剣呑な空気が漂っていて、
口から放たれたセリフには、明らかにこういった連中や揉め事に場慣れしている者の言葉が含まれていた。
「い……いや、それには及ばねえよ」
「そうかい?」
ここでようやく、遊水は男の手を放して、
男たちが、一斉に遊水から離れた。
「じゃあ、後で親分さんのとこには、知り合いが子分さんに面倒かけたと俺から挨拶に行っとくぜ」
ニヤニヤしたままそう言った遊水に、「カンベンしてくれ!」とチンピラたちは悲鳴を上げた。
「親分からは、あんたとは絶対に揉め事を起こすなって言われてンだ。
た、頼むから、このことは……」
「ふん、黙っててやるよ。とっとと失せな」
遊水のその言葉を合図に、
捨てゼリフも何もなく、脱兎の如く引き上げて行った男たちの背中を、私はあっけにとられて眺めていた。
思いがけない再会に驚くと同時に──私は、彼をこんな場面に巻き込んでしまったことに背筋が冷たくなったのだが、
「げ!? 遊水かよ」
この金髪の美青年を目にした途端、チンピラたちは青くなった。
知り合いらしく、名前までズバリ合っていた。
「てめえら、見たところ銀治郎親分さんところの若い奴らだな。この女は俺の恩人なんだが、どうかしたかい?」
「うえっ!? い、いや……」
「話をつける必要があるんなら、俺が親分さんのとこに行くぜ? 案内しな」
遊水の白い顔に貼りついた冷ややかな笑いや、チンピラたちに向けた刃物のような目つきは──そこらの町人や優男とは一線を画する剣呑な空気が漂っていて、
口から放たれたセリフには、明らかにこういった連中や揉め事に場慣れしている者の言葉が含まれていた。
「い……いや、それには及ばねえよ」
「そうかい?」
ここでようやく、遊水は男の手を放して、
男たちが、一斉に遊水から離れた。
「じゃあ、後で親分さんのとこには、知り合いが子分さんに面倒かけたと俺から挨拶に行っとくぜ」
ニヤニヤしたままそう言った遊水に、「カンベンしてくれ!」とチンピラたちは悲鳴を上げた。
「親分からは、あんたとは絶対に揉め事を起こすなって言われてンだ。
た、頼むから、このことは……」
「ふん、黙っててやるよ。とっとと失せな」
遊水のその言葉を合図に、
捨てゼリフも何もなく、脱兎の如く引き上げて行った男たちの背中を、私はあっけにとられて眺めていた。