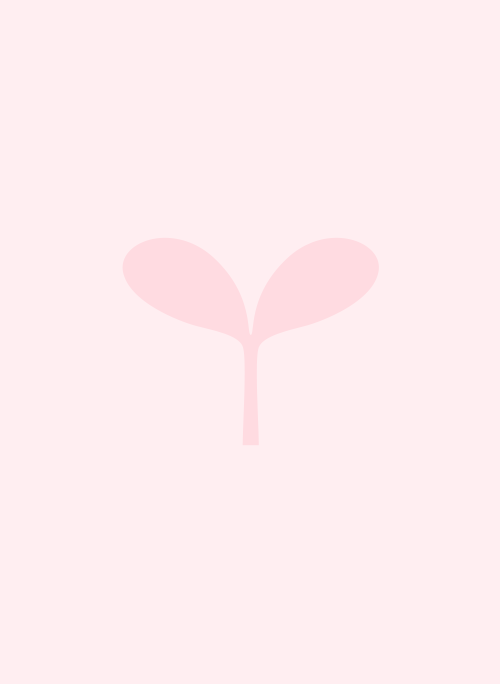その日、私は仕上がった絵を依頼主の商家に届けた帰りで、本格的に熱くなり始めた夏の空の下を自分の長屋に向かって歩いていた。
この時もまだ私は、突然舞い込んできていなくなった男のことをぼんやりと考えていて、
要するに注意力散漫になっていた。
くそ、何なのだあいつは。
人の心を散々掻き乱しておいて、挨拶もなしに勝手に消えるとは……!
などと、胸の内で一人憤ったりしつつ大きく一歩踏み出した瞬間、私は思い切り人にぶつかってしまった。
人通りの多い町中の往来のど真ん中だった。
「失礼をした」と、慌てて謝ってそそくさと立ち去ろうとすると、
「おう、待ちなこのアマ」
と、私がぶつかった相手がガラの悪い声を出し、連れと思しきチンピラの如き格好をした男たちが行く手を塞いだ。
「てめえ、アニキにぶつかっておいて謝っただけですまそうってのか?」
行く手を阻んだ者たちがドスの利いた声で言うのを聞いて、しまったマズい相手に捕まったと思った。
人目も気にせずに私を囲む三、四人の男たちは、見るからにまともではない──無頼の輩といった風体で、まあ言ってみるならば出会った時の円士郎みたいな印象の連中だった。
「へえ! アニキ、よく見りゃこの女、凄え美人ですぜ」
私の顔を覗き込んで、男たちは嬉しそうにそう言った。
普通の町娘ならば、こういう時恐怖に震え上がって泣き出すものなのかもしれないし、
泣いて見せなくとも、せめてしおらしくしていれば良かったのかもしれないが、
この時私は暑さのせいなのか、消えたあいつのせいなのか、イライラしていて、
「なんだ、私がぶつかったそこの貧相な顔の男は、どこぞの御大尽様か何かか? 謝って済まねばどうする? 無礼討ちにでもするか? それでもこの場で自害でもせよと言う気か?」
正面切って噛みついてしまった。
「なにィ!?」
たちまち男たちの顔色が変わった。
私は構わずに、
「そんな真似をさせたくば、政敵を失脚させて今頃あそこに見えている城で好き放題やっている御家老様でも連れてくるのだね!」
そんな風に、父と共に雨宮家を没落させた城代家老への怒りまでこんな場所でぶちまけた。
この時もまだ私は、突然舞い込んできていなくなった男のことをぼんやりと考えていて、
要するに注意力散漫になっていた。
くそ、何なのだあいつは。
人の心を散々掻き乱しておいて、挨拶もなしに勝手に消えるとは……!
などと、胸の内で一人憤ったりしつつ大きく一歩踏み出した瞬間、私は思い切り人にぶつかってしまった。
人通りの多い町中の往来のど真ん中だった。
「失礼をした」と、慌てて謝ってそそくさと立ち去ろうとすると、
「おう、待ちなこのアマ」
と、私がぶつかった相手がガラの悪い声を出し、連れと思しきチンピラの如き格好をした男たちが行く手を塞いだ。
「てめえ、アニキにぶつかっておいて謝っただけですまそうってのか?」
行く手を阻んだ者たちがドスの利いた声で言うのを聞いて、しまったマズい相手に捕まったと思った。
人目も気にせずに私を囲む三、四人の男たちは、見るからにまともではない──無頼の輩といった風体で、まあ言ってみるならば出会った時の円士郎みたいな印象の連中だった。
「へえ! アニキ、よく見りゃこの女、凄え美人ですぜ」
私の顔を覗き込んで、男たちは嬉しそうにそう言った。
普通の町娘ならば、こういう時恐怖に震え上がって泣き出すものなのかもしれないし、
泣いて見せなくとも、せめてしおらしくしていれば良かったのかもしれないが、
この時私は暑さのせいなのか、消えたあいつのせいなのか、イライラしていて、
「なんだ、私がぶつかったそこの貧相な顔の男は、どこぞの御大尽様か何かか? 謝って済まねばどうする? 無礼討ちにでもするか? それでもこの場で自害でもせよと言う気か?」
正面切って噛みついてしまった。
「なにィ!?」
たちまち男たちの顔色が変わった。
私は構わずに、
「そんな真似をさせたくば、政敵を失脚させて今頃あそこに見えている城で好き放題やっている御家老様でも連れてくるのだね!」
そんな風に、父と共に雨宮家を没落させた城代家老への怒りまでこんな場所でぶちまけた。