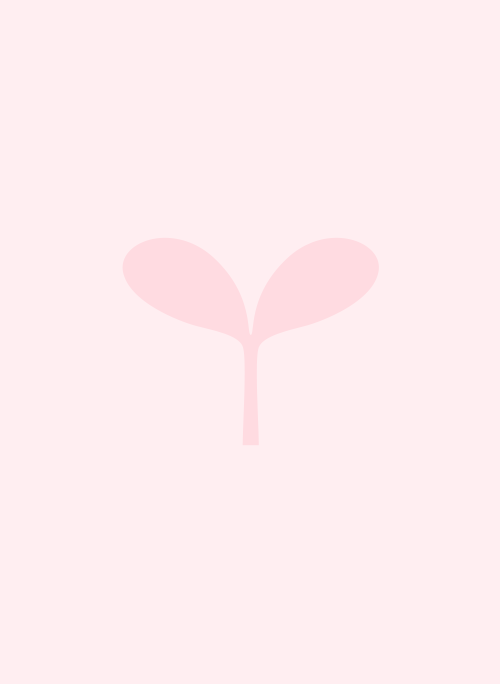この夜も、例によって私の長屋の戸は深夜にいきなり蹴り開けられた。
強盗以外にこんな真似をする者は当然一人しかおらず、戸口に立っていたのはいつもどおり結城円士郎だった。
私もなんだか慣れてしまっていて、鶏をさばいていた包丁を握ったまま彼に文句を言ったりして──
──こんなことに慣れるのもどうかとは思ったが。
しかしこの夜は、これまでとやや違っていた。
円士郎は一人ではなかった。
彼は肩に、法被に股引という町人風の格好をした男を担ぎ上げていて、
そして彼の後ろからは、ひょこりと小柄な少年が顔を出した。
奇妙なことに、こちらは寝床から抜け出してきたような寝間着姿で、
抜けるように白い肌を戸口の闇に浮かび上がらせ、
つややかな漆黒の総髪を円士郎と同じように一まとめにした──
驚くべき美貌の少年だった。
まだ元服前というところか。
円士郎の更に上を行く美童だ。
結城家の御曹司と、町人風の男と、寝間着姿の少年。
どういう組み合わせの三人なのかと首を捻り──、
──私は息を呑む。
諸君らの時代のように明るい電灯というものがないこの時代、
夜の闇は深い。
暗い灯りではすぐには気がつけなかったが、
よくよく見ると彼らは三人とも血まみれだったのだ。
強盗以外にこんな真似をする者は当然一人しかおらず、戸口に立っていたのはいつもどおり結城円士郎だった。
私もなんだか慣れてしまっていて、鶏をさばいていた包丁を握ったまま彼に文句を言ったりして──
──こんなことに慣れるのもどうかとは思ったが。
しかしこの夜は、これまでとやや違っていた。
円士郎は一人ではなかった。
彼は肩に、法被に股引という町人風の格好をした男を担ぎ上げていて、
そして彼の後ろからは、ひょこりと小柄な少年が顔を出した。
奇妙なことに、こちらは寝床から抜け出してきたような寝間着姿で、
抜けるように白い肌を戸口の闇に浮かび上がらせ、
つややかな漆黒の総髪を円士郎と同じように一まとめにした──
驚くべき美貌の少年だった。
まだ元服前というところか。
円士郎の更に上を行く美童だ。
結城家の御曹司と、町人風の男と、寝間着姿の少年。
どういう組み合わせの三人なのかと首を捻り──、
──私は息を呑む。
諸君らの時代のように明るい電灯というものがないこの時代、
夜の闇は深い。
暗い灯りではすぐには気がつけなかったが、
よくよく見ると彼らは三人とも血まみれだったのだ。