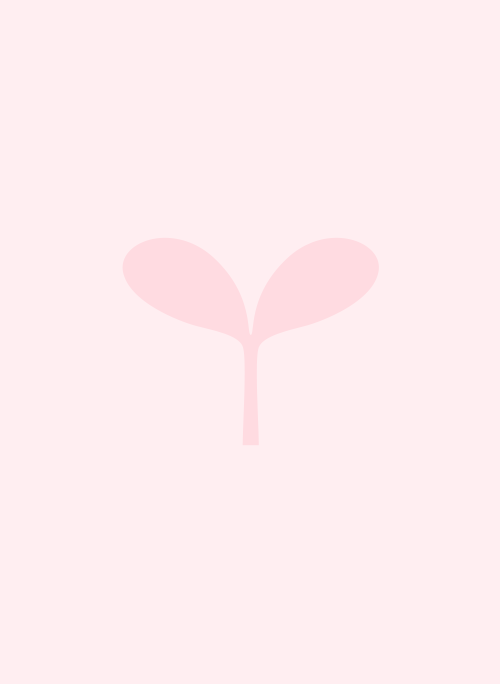彼が眠りたいのなら寝床を貸してやるつもりだったが、
円士郎は作業をしている私の横で、
私の絵や、
絵の資料として長屋に置いてある本草学の書物や、
びいどろの瓶に入った酒漬けのマムシなどを興味津々に眺めていて、
どうやら寝る気は皆無のようだった。
彼は私の絵について、何故そんな変わった絵ばかり描くのかと尋ね、私が説明するとちゃんと理解を示してくれて、
私のものの捉え方や考え方は共感できると言ってくれた。
実際に話してみてわかったのだが、結城円士郎は世間一般で噂されている素行の悪さからは想像できない程の、高い教養を備えていた。
考えてみれば、結城家ほどの名家の跡取りなのだから、英才教育を施されていて当たり前ではあるのだが。
彼は私の思考が西洋の進んだ学問を支えている主義思想に近いのだと指摘して、
自分も西洋の合理的なものの考え方は好きだと語り──
──おそらく、虹庵が我々を似ていると評したのはこのためだったのだろう。
「しかしあんたが女だったってことは──虹庵とあんたはやっぱり恋仲か?」
話の中で円士郎がそんなことを言って、私は思わず下図の線を描き損ねそうになった。
「違うのか?」
円士郎は意外そうに、
「男の家に若い女が足繁く通ってた、ってことになるだろ?」
「……虹庵先生のことは尊敬しているし、
人柄は好きだし、
師として慕っているつもりだが、
そのような目で見たことはない」
「あんたがそうでも、先生のほうが手を出してきたりはしなかったのかよ?」
「君と一緒にするな。
先生がそんな真似をするワケがなかろう」
私が憮然としながら否定すると、円士郎は「へえ、意外と男ってもんがわかってねえんだな」と言って──
──後に私は、このときの円士郎の言葉の意味を痛感することになる。
円士郎は作業をしている私の横で、
私の絵や、
絵の資料として長屋に置いてある本草学の書物や、
びいどろの瓶に入った酒漬けのマムシなどを興味津々に眺めていて、
どうやら寝る気は皆無のようだった。
彼は私の絵について、何故そんな変わった絵ばかり描くのかと尋ね、私が説明するとちゃんと理解を示してくれて、
私のものの捉え方や考え方は共感できると言ってくれた。
実際に話してみてわかったのだが、結城円士郎は世間一般で噂されている素行の悪さからは想像できない程の、高い教養を備えていた。
考えてみれば、結城家ほどの名家の跡取りなのだから、英才教育を施されていて当たり前ではあるのだが。
彼は私の思考が西洋の進んだ学問を支えている主義思想に近いのだと指摘して、
自分も西洋の合理的なものの考え方は好きだと語り──
──おそらく、虹庵が我々を似ていると評したのはこのためだったのだろう。
「しかしあんたが女だったってことは──虹庵とあんたはやっぱり恋仲か?」
話の中で円士郎がそんなことを言って、私は思わず下図の線を描き損ねそうになった。
「違うのか?」
円士郎は意外そうに、
「男の家に若い女が足繁く通ってた、ってことになるだろ?」
「……虹庵先生のことは尊敬しているし、
人柄は好きだし、
師として慕っているつもりだが、
そのような目で見たことはない」
「あんたがそうでも、先生のほうが手を出してきたりはしなかったのかよ?」
「君と一緒にするな。
先生がそんな真似をするワケがなかろう」
私が憮然としながら否定すると、円士郎は「へえ、意外と男ってもんがわかってねえんだな」と言って──
──後に私は、このときの円士郎の言葉の意味を痛感することになる。