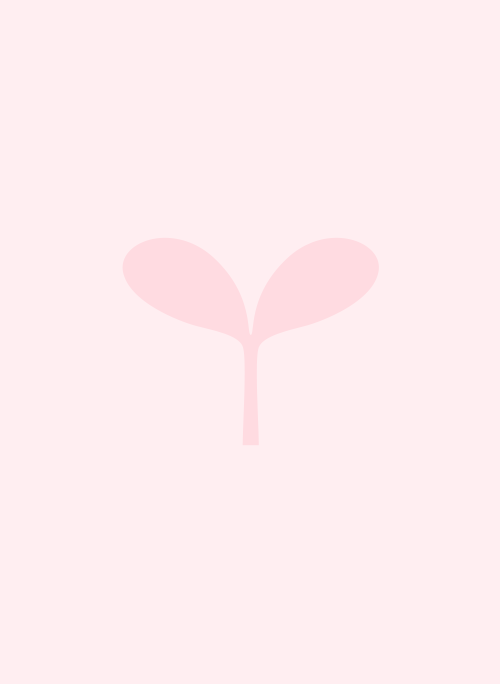「ワケがわからねェな」
と遊水が苦笑して、
「円士郎様」と、私たちの共通の、その大切な友人の名を呼んだ。
「一匹どうぞ。タダにしといてやるぜ」
そう言って、白い指がタライで泳ぐ赤い魚を指さす。
「おいおい、冗談だろ」
円士郎は顔をしかめた。
「こんな場所でもらったって、どうやって屋敷まで持って帰れってんだよ」
遊水は縁台の下に置いていた、びいどろの玉を一つ取り上げた。
ちょうど先刻の物売りがたくさんつり下げていた風鈴を逆さまにして、紐でつるせるようにした形をしている。
「何だそれ?」
円士郎が目を瞬いた。
「金魚玉というものだよ」と、私は一年前を懐かしく思い出しながら言った。
「金魚玉?」
眉間に皺を作る円士郎の前で、遊水はいつかのようにタライの中の赤い魚を水ごと一匹すくって透明なびいどろの中に入れた。
と遊水が苦笑して、
「円士郎様」と、私たちの共通の、その大切な友人の名を呼んだ。
「一匹どうぞ。タダにしといてやるぜ」
そう言って、白い指がタライで泳ぐ赤い魚を指さす。
「おいおい、冗談だろ」
円士郎は顔をしかめた。
「こんな場所でもらったって、どうやって屋敷まで持って帰れってんだよ」
遊水は縁台の下に置いていた、びいどろの玉を一つ取り上げた。
ちょうど先刻の物売りがたくさんつり下げていた風鈴を逆さまにして、紐でつるせるようにした形をしている。
「何だそれ?」
円士郎が目を瞬いた。
「金魚玉というものだよ」と、私は一年前を懐かしく思い出しながら言った。
「金魚玉?」
眉間に皺を作る円士郎の前で、遊水はいつかのようにタライの中の赤い魚を水ごと一匹すくって透明なびいどろの中に入れた。