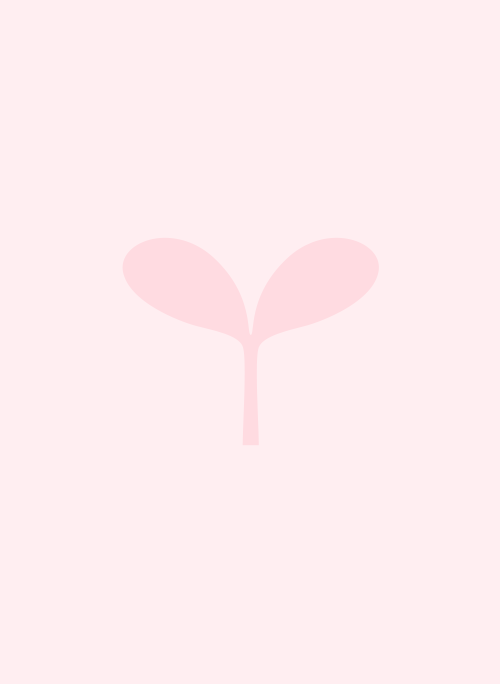円士郎は家老の下に置かれた番方の役目に就いた後もこのとおり、暇さえ有れば遊び回っているようだ。
「上役としては、どうなのだね? こういう下役を持ったご感想は」
「ん~? 俺も今は、他人のことをとやかく言える立場じゃねえからなァ」
私の問いかけに対して、
隣に片胡座で座って串団子を食べていた遊水こと青文は苦笑した。
「その格好はなんだよ鳥英!? 遊水のほうはともかくよォ」
今の円士郎にだけは格好についてどうこう言われたくない気がするが──近くまで歩いてきて目を丸くしている円士郎が指摘するとおり、
出会った時の法被姿に身を包み、棒手振の遊水の格好をした青文はいつものことなのだが、
今日は私も武家の奥方の格好ではなく、鳥英として暮らしていた頃の町娘の格好をしている。
つまりは──この格好で屋敷を抜け出して、
お供ナシ、二人っきりのお忍びデートの真っ最中なのだった。
一目見るなり、私たちを「青文」と「亜鳥」ではなく、「遊水」と「鳥英」と呼んだ円士郎に、私は舌を巻く。
振り返ると、彼はこれまで遊水の正体を知りつつも、ただの一度も私たちの前で彼の名前を呼び間違えたことがなかった。
この辺りの抜かりの無さは、彼の信頼できる部分だ。
……私とはエラい違いである。
自分で思い出してまた頬が火照るのを感じて、私は慌てて考えを振り払って、
「ここにいれば、円士郎殿と会える気がしたのでね」
と、私たちが先刻から座っている──三舟屋の店先に置かれた縁台を示した。
「上役としては、どうなのだね? こういう下役を持ったご感想は」
「ん~? 俺も今は、他人のことをとやかく言える立場じゃねえからなァ」
私の問いかけに対して、
隣に片胡座で座って串団子を食べていた遊水こと青文は苦笑した。
「その格好はなんだよ鳥英!? 遊水のほうはともかくよォ」
今の円士郎にだけは格好についてどうこう言われたくない気がするが──近くまで歩いてきて目を丸くしている円士郎が指摘するとおり、
出会った時の法被姿に身を包み、棒手振の遊水の格好をした青文はいつものことなのだが、
今日は私も武家の奥方の格好ではなく、鳥英として暮らしていた頃の町娘の格好をしている。
つまりは──この格好で屋敷を抜け出して、
お供ナシ、二人っきりのお忍びデートの真っ最中なのだった。
一目見るなり、私たちを「青文」と「亜鳥」ではなく、「遊水」と「鳥英」と呼んだ円士郎に、私は舌を巻く。
振り返ると、彼はこれまで遊水の正体を知りつつも、ただの一度も私たちの前で彼の名前を呼び間違えたことがなかった。
この辺りの抜かりの無さは、彼の信頼できる部分だ。
……私とはエラい違いである。
自分で思い出してまた頬が火照るのを感じて、私は慌てて考えを振り払って、
「ここにいれば、円士郎殿と会える気がしたのでね」
と、私たちが先刻から座っている──三舟屋の店先に置かれた縁台を示した。