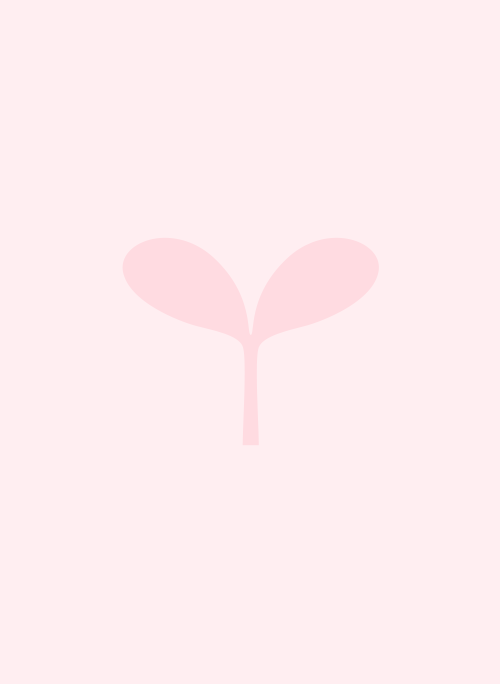湯飲みのお茶をすすって、私は足下の金魚を見下ろす。
「考えてみると──四月から仕事で忙しくなるというのは金魚の盆栽のことではなくて、城代の仕事のことだったのだな」
「まァな。一応、金魚の仔も春にとれるんだがねェ」
諸君らは歴史の時間に参勤交代なるものを習っていると思うが。
幕府が定めたこの、大名が江戸と国元を一年置きに往復するという制度のため、
今年は殿様が参勤交代で江戸に行く年で、例えば円士郎の父君の結城家現当主晴蔵様なども殿様に付き従って四月から江戸に行っているのだ。
藩主が留守の間、国元で政治の実権を任されるのが城代家老だった。
「ん? じゃあ、よく江戸に行くというのは?」
「あァ。跡目を継いで城代になる前は、殿様に気に入られてよく供で江戸に行っていた。
今も、殿が国元にいる間は、ちょくちょく……な」
「金魚を売りに?」
「当然それもあるし、他にも所用でね。
この次は、亜鳥の絵も持って行って向こうの御仁に見せて来るかな」
やれやれ。
私は溜息を吐く。
この分だと──以前聞いた、阿蘭陀の本草学の書物とも呼べる貴重な絵図を見せてくれた江戸の御仁というのも、
一国の家老クラスの身分の者でなければ会えないような相手だったのだろう。
「あれえ!? 遊水に鳥英!? お前ら、何やってるんだ!?」
人混みの向こうから声がかかって、そちらを見ると
派手な着流しを着て、二十一世紀のアレンジヘアさながらに髪を結い上げ女物の簪(かんざし)と髪紐で飾った、一本差し姿の若い侍がこちらに歩いて来るところだった。
言わずと知れた結城の放蕩息子、円士郎である。
「考えてみると──四月から仕事で忙しくなるというのは金魚の盆栽のことではなくて、城代の仕事のことだったのだな」
「まァな。一応、金魚の仔も春にとれるんだがねェ」
諸君らは歴史の時間に参勤交代なるものを習っていると思うが。
幕府が定めたこの、大名が江戸と国元を一年置きに往復するという制度のため、
今年は殿様が参勤交代で江戸に行く年で、例えば円士郎の父君の結城家現当主晴蔵様なども殿様に付き従って四月から江戸に行っているのだ。
藩主が留守の間、国元で政治の実権を任されるのが城代家老だった。
「ん? じゃあ、よく江戸に行くというのは?」
「あァ。跡目を継いで城代になる前は、殿様に気に入られてよく供で江戸に行っていた。
今も、殿が国元にいる間は、ちょくちょく……な」
「金魚を売りに?」
「当然それもあるし、他にも所用でね。
この次は、亜鳥の絵も持って行って向こうの御仁に見せて来るかな」
やれやれ。
私は溜息を吐く。
この分だと──以前聞いた、阿蘭陀の本草学の書物とも呼べる貴重な絵図を見せてくれた江戸の御仁というのも、
一国の家老クラスの身分の者でなければ会えないような相手だったのだろう。
「あれえ!? 遊水に鳥英!? お前ら、何やってるんだ!?」
人混みの向こうから声がかかって、そちらを見ると
派手な着流しを着て、二十一世紀のアレンジヘアさながらに髪を結い上げ女物の簪(かんざし)と髪紐で飾った、一本差し姿の若い侍がこちらに歩いて来るところだった。
言わずと知れた結城の放蕩息子、円士郎である。