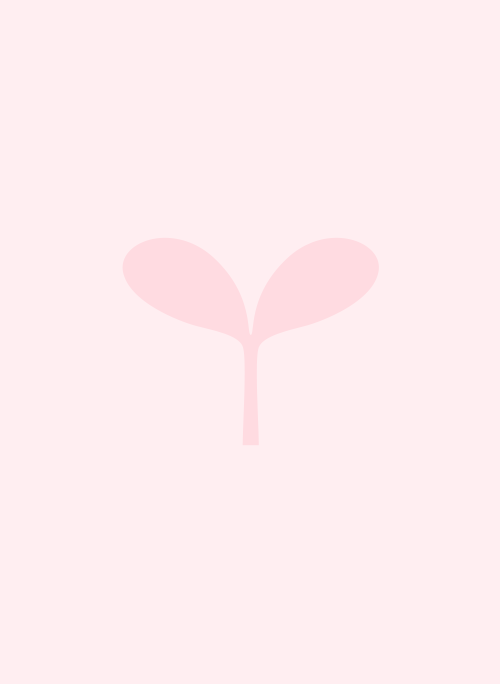朝の光の中で黙ったまましばらくそうやって抱き合って、
私は彼の腕の中でクスリとした。
「遊水は、もう現れないんじゃなかったのか?」
少し意地悪く言うと、彼の笑っている振動が伝わってきて、
「抱いてる最中あれだけそっちの名で呼ばれりゃァな。現れてやろうかって気にもなるぜ?」
私は顔から火が出るかと思うほど真っ赤になってしまった。
昨日の夜、私は彼を結局その名で呼んでいたのか。
「まァ、屋敷の中ではその名は禁止だが、寝屋の中でだけならそっちで呼ぶのも許してやるよ」
からかうような声音で言われ──
どうやら完敗だった。
うう、クソ……
悔しいが、意地悪勝負では全く勝ち目がないようだ。
「それに、ここ数年遊水として動いてみてよくわかったしな」
「……何がだ?」
少し体を離して、鼻白む私の顔を見つめて、彼はにやっとした。
「俺はこっちが素だ」
私は彼の腕の中でクスリとした。
「遊水は、もう現れないんじゃなかったのか?」
少し意地悪く言うと、彼の笑っている振動が伝わってきて、
「抱いてる最中あれだけそっちの名で呼ばれりゃァな。現れてやろうかって気にもなるぜ?」
私は顔から火が出るかと思うほど真っ赤になってしまった。
昨日の夜、私は彼を結局その名で呼んでいたのか。
「まァ、屋敷の中ではその名は禁止だが、寝屋の中でだけならそっちで呼ぶのも許してやるよ」
からかうような声音で言われ──
どうやら完敗だった。
うう、クソ……
悔しいが、意地悪勝負では全く勝ち目がないようだ。
「それに、ここ数年遊水として動いてみてよくわかったしな」
「……何がだ?」
少し体を離して、鼻白む私の顔を見つめて、彼はにやっとした。
「俺はこっちが素だ」