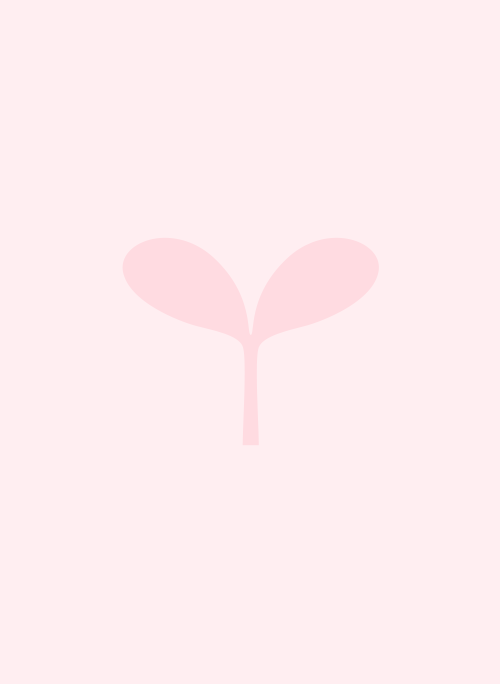「へェ?」
青文が金色の眉を少しだけ上げて、嬉しそうな顔になった。
私はそれだけで舞い上がってしまって、抑えようとしていた動悸が再び激しくなった。
「そいつァお仕置きじゃなくて、お礼をしなきゃならねェかな?」
「き……気持ちだけもらっておく……っ」
またまた艶っぽくニヤリとされて、私が焦りながら手を振ると、青文は肩を揺らして笑った。
私は大きく息を吐いた。
「その時、奉公人たちと言葉を交わしたら、私は涙を流して同情されたぞ」
先刻の出来事を思い出して、私はげんなりしながら旦那様の綺麗な顔を見つめた。
「あなたは家の者たちにいったいどういう印象を与えてるんだ? 有り得ないくらい怯えていたが。
私は化け物に嫁いだ人身御供かと叫びたくなった」
クックッと彼はおかしそうに喉を鳴らして、
「まァ、城中での評価とほぼ同じ印象になるよう振る舞っているつもりだ」
と答えた。
私は切なくなった。
「どうしてそんな……嫌われるような──怖がられるような振る舞い方をするのだ?
あなたは優しい人なのに……」
「そのほうが都合がいい。近寄りがたいと思われたほうが、素顔が露見する危険も少なくなるからな」
「そんな……」
私は改めて、いつも彼がどれほどの孤独の中にいるのかを知って胸が締めつけられた。
青文は微笑を湛えたままじっと私に視線を送って、それからふわりと優しく抱き締めてくれた。
「は。俺のそばにはいつも亜鳥がいてくれるんだろ? だったらそれで十分だ」
穏やかな声がそう告げた。
私はぎゅっと、彼を抱き締め返す。
青文が金色の眉を少しだけ上げて、嬉しそうな顔になった。
私はそれだけで舞い上がってしまって、抑えようとしていた動悸が再び激しくなった。
「そいつァお仕置きじゃなくて、お礼をしなきゃならねェかな?」
「き……気持ちだけもらっておく……っ」
またまた艶っぽくニヤリとされて、私が焦りながら手を振ると、青文は肩を揺らして笑った。
私は大きく息を吐いた。
「その時、奉公人たちと言葉を交わしたら、私は涙を流して同情されたぞ」
先刻の出来事を思い出して、私はげんなりしながら旦那様の綺麗な顔を見つめた。
「あなたは家の者たちにいったいどういう印象を与えてるんだ? 有り得ないくらい怯えていたが。
私は化け物に嫁いだ人身御供かと叫びたくなった」
クックッと彼はおかしそうに喉を鳴らして、
「まァ、城中での評価とほぼ同じ印象になるよう振る舞っているつもりだ」
と答えた。
私は切なくなった。
「どうしてそんな……嫌われるような──怖がられるような振る舞い方をするのだ?
あなたは優しい人なのに……」
「そのほうが都合がいい。近寄りがたいと思われたほうが、素顔が露見する危険も少なくなるからな」
「そんな……」
私は改めて、いつも彼がどれほどの孤独の中にいるのかを知って胸が締めつけられた。
青文は微笑を湛えたままじっと私に視線を送って、それからふわりと優しく抱き締めてくれた。
「は。俺のそばにはいつも亜鳥がいてくれるんだろ? だったらそれで十分だ」
穏やかな声がそう告げた。
私はぎゅっと、彼を抱き締め返す。