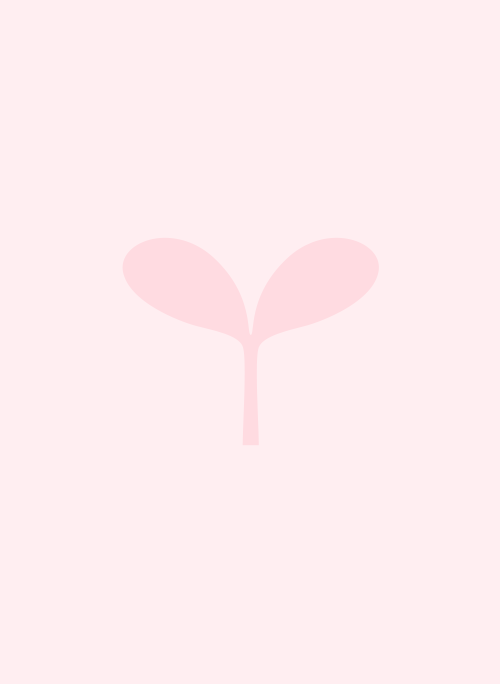そんなことを考えているうちに、後ろから抱きすくめられ、青文が首筋に顔を埋めてきた。
思わず身を仰け反らせる。
「どうした、亜鳥。言えねえようなことなのかい」
するりと着物の胸元から彼の手が滑り込み、肌に触れた。
「──っあ……」
無理だ。
答えようとしても言葉にならない。
自分でも信じられないような声が出ただけだった。
って、ワザとか!
確信犯か!
私は昨夜初めて男を知ったんだぞ?
やめてくれ。
そんな抵抗力のない私に、朝っぱらから何してくれるんだこの男は……!
私の心の叫びも虚しく──
「それともこのままお仕置きをして欲しいのかな?」
愛撫の手を止めず、
耳元でくすくす笑って、彼は片手で私の顔を横に向かせて、
「……やめて──」
動かしかけた唇を吸われる。
私は何だか色々諦めた。
しばらくいいように弄ばれて、全身の肌がすっかり上気した頃、ようやく青文は笑いながら私の身を放してくれた。
恐ろしい事に、私の着物も髪もほとんど乱されていなかった。
「だ……旦那様に手料理を、と思って、朝餉の支度をしていたのだよ」
私は何とか息と動悸を整えながら、涙目で青文を睨んだ。
思わず身を仰け反らせる。
「どうした、亜鳥。言えねえようなことなのかい」
するりと着物の胸元から彼の手が滑り込み、肌に触れた。
「──っあ……」
無理だ。
答えようとしても言葉にならない。
自分でも信じられないような声が出ただけだった。
って、ワザとか!
確信犯か!
私は昨夜初めて男を知ったんだぞ?
やめてくれ。
そんな抵抗力のない私に、朝っぱらから何してくれるんだこの男は……!
私の心の叫びも虚しく──
「それともこのままお仕置きをして欲しいのかな?」
愛撫の手を止めず、
耳元でくすくす笑って、彼は片手で私の顔を横に向かせて、
「……やめて──」
動かしかけた唇を吸われる。
私は何だか色々諦めた。
しばらくいいように弄ばれて、全身の肌がすっかり上気した頃、ようやく青文は笑いながら私の身を放してくれた。
恐ろしい事に、私の着物も髪もほとんど乱されていなかった。
「だ……旦那様に手料理を、と思って、朝餉の支度をしていたのだよ」
私は何とか息と動悸を整えながら、涙目で青文を睨んだ。