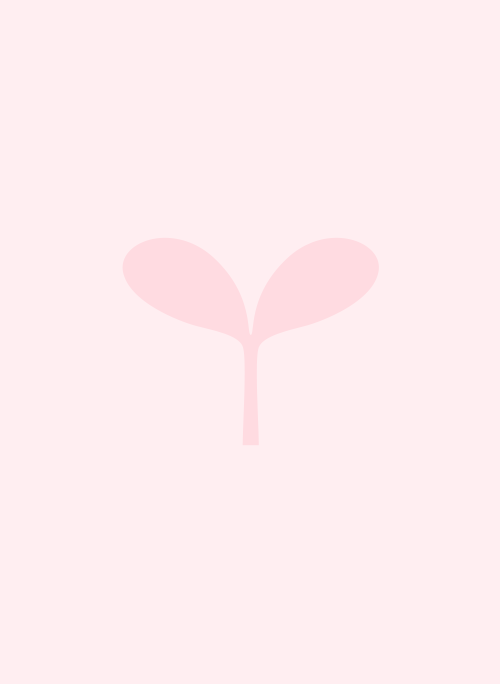ちょうど朝日が昇る頃、朝餉の支度を終えた私が再び寝所に戻ると、彼は起きていて、部屋の壁に寄りかかって座り、鉢の中の金魚を眺めていた。
美しい翠玉の瞳が動いて、立ち尽くす私を捉えて
下ろしたままの金の髪と、少しはだけた寝間着に、私の心臓は大きな音を立てた。
「おいこら、初日の朝から旦那様を置き去りにするとはいい度胸じゃねえかい」
と、耳慣れた口調で言って、彼がニヤリとした。
「遊水……」
私が寝所の入り口に立ったままその名を呟くと、彼は立ち上がって私のほうに歩いてきて、
開きっぱなしになっている部屋の襖を私の後ろで閉めた。
「ここでそっちの名は呼ぶな」と、そのまま襖に軽く手をついて私を見下ろし、白い口元が囁いた。
襖と彼とに後ろと前を挟まれて、私は壁際に追いつめられたような格好になって、どきどきする胸を押さえた。
明るい光の中、至近距離で私を見つめる寝間着姿の彼にはぞくりとするような色気が漂っていて、
昨晩の睦みごとが蘇り、私の頬に朱が上る。
ククッと、喉を鳴らして彼がそのまま唇を私の首筋に這わせた。
「あ……」
全身の力が抜けるようなとんでもない快感が走って、思わず声を漏らした私に、
「『青文殿』か『旦那様』だ、言ってみな」
甘い吐息のような声が耳元をくすぐった。
「青文……殿……」
崩れ落ちそうになりながら陶然と名を呼んだ私の唇を彼の唇が塞ぎ、深い口づけを落として、
「よろしい」
私の唇を解放した青文は、震える息をつく私にそう言って笑んだ。
美しい翠玉の瞳が動いて、立ち尽くす私を捉えて
下ろしたままの金の髪と、少しはだけた寝間着に、私の心臓は大きな音を立てた。
「おいこら、初日の朝から旦那様を置き去りにするとはいい度胸じゃねえかい」
と、耳慣れた口調で言って、彼がニヤリとした。
「遊水……」
私が寝所の入り口に立ったままその名を呟くと、彼は立ち上がって私のほうに歩いてきて、
開きっぱなしになっている部屋の襖を私の後ろで閉めた。
「ここでそっちの名は呼ぶな」と、そのまま襖に軽く手をついて私を見下ろし、白い口元が囁いた。
襖と彼とに後ろと前を挟まれて、私は壁際に追いつめられたような格好になって、どきどきする胸を押さえた。
明るい光の中、至近距離で私を見つめる寝間着姿の彼にはぞくりとするような色気が漂っていて、
昨晩の睦みごとが蘇り、私の頬に朱が上る。
ククッと、喉を鳴らして彼がそのまま唇を私の首筋に這わせた。
「あ……」
全身の力が抜けるようなとんでもない快感が走って、思わず声を漏らした私に、
「『青文殿』か『旦那様』だ、言ってみな」
甘い吐息のような声が耳元をくすぐった。
「青文……殿……」
崩れ落ちそうになりながら陶然と名を呼んだ私の唇を彼の唇が塞ぎ、深い口づけを落として、
「よろしい」
私の唇を解放した青文は、震える息をつく私にそう言って笑んだ。