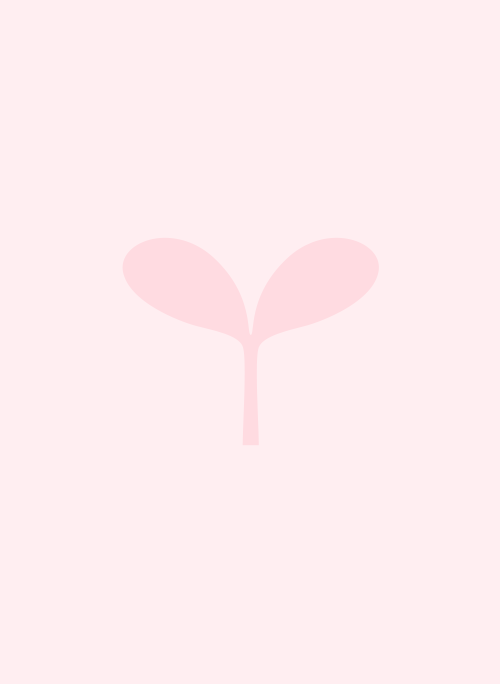薄明るい光を感じて、私は瞼を開いた。
淡い光が障子越しに部屋の中をうっすらと照らしている。
弾かれたように上半身を起こして、隣を見る。
いつもいつも私が目覚めると天女の如く消えていた男は、しかし今朝は天に帰ることなくそこにいた。
金色の不思議な髪が、日の出前の薄明の中でぼうっと浮かび上がって見える。
雪か氷で作られた彫刻のような白い顔がこちらを向いて、静かな寝息を立てていた。
こうして見ても抜けるように白い肌だった。
いつもいつも覆面などを被っていたのならそれも納得だな、などと寝起きの頭でぼんやり考えて、
険の抜けた安らかな寝顔を見下ろしていたら、幸せな気分になった。
これからはずっと、こうして彼は消えずに隣にいるのかと少し信じられないような気もして、
急に胸がどきどきし始めてしまった。
もう一度彼の横に潜り込んで、胸元に顔を埋める。
しばらくそのまま微睡んで、それから思い立ってそっと寝屋を抜け出した。
カナカナカナ……と、夏の早朝のヒグラシの声が聞こえている。
まだ屋敷の主が起き出すには早い刻限だが、奉公人たちは既に起きて働き出していた。
私は身支度を整えて女中に場所を聞き、ひんやりした心地良い風を感じながら庭に面した廊下を渡り、朝餉の支度に忙しく人の行き交う屋敷の台所に顔を出した。
淡い光が障子越しに部屋の中をうっすらと照らしている。
弾かれたように上半身を起こして、隣を見る。
いつもいつも私が目覚めると天女の如く消えていた男は、しかし今朝は天に帰ることなくそこにいた。
金色の不思議な髪が、日の出前の薄明の中でぼうっと浮かび上がって見える。
雪か氷で作られた彫刻のような白い顔がこちらを向いて、静かな寝息を立てていた。
こうして見ても抜けるように白い肌だった。
いつもいつも覆面などを被っていたのならそれも納得だな、などと寝起きの頭でぼんやり考えて、
険の抜けた安らかな寝顔を見下ろしていたら、幸せな気分になった。
これからはずっと、こうして彼は消えずに隣にいるのかと少し信じられないような気もして、
急に胸がどきどきし始めてしまった。
もう一度彼の横に潜り込んで、胸元に顔を埋める。
しばらくそのまま微睡んで、それから思い立ってそっと寝屋を抜け出した。
カナカナカナ……と、夏の早朝のヒグラシの声が聞こえている。
まだ屋敷の主が起き出すには早い刻限だが、奉公人たちは既に起きて働き出していた。
私は身支度を整えて女中に場所を聞き、ひんやりした心地良い風を感じながら庭に面した廊下を渡り、朝餉の支度に忙しく人の行き交う屋敷の台所に顔を出した。