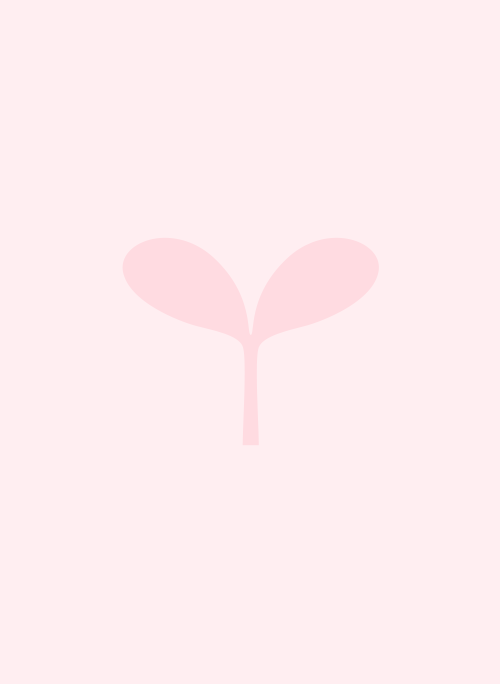肌の上を唇が伝う。
吐息が漏れる。
「亜鳥」
彼が私の名前を呼ぶ。
体の芯が痺れていく。
気づけば行灯の火は消えて、
水底のような青い夜の帷に包まれていた。
「亜鳥」と、彼が繰り返す。
ぱしゃんと音を立て、部屋の隅に置かれた陶器の中の金魚がはねた気がした。
ゆらゆらと世界が水の中で溶けてゆくのを感じながら、
私は何度も、何度も、愛しい人の名を呼んだ。
どちらの名を呼んでいたのか、自分でもわからなかった。
いつの間にか再び鳴き始めた虫の声が、遠く聞こえていた。
吐息が漏れる。
「亜鳥」
彼が私の名前を呼ぶ。
体の芯が痺れていく。
気づけば行灯の火は消えて、
水底のような青い夜の帷に包まれていた。
「亜鳥」と、彼が繰り返す。
ぱしゃんと音を立て、部屋の隅に置かれた陶器の中の金魚がはねた気がした。
ゆらゆらと世界が水の中で溶けてゆくのを感じながら、
私は何度も、何度も、愛しい人の名を呼んだ。
どちらの名を呼んでいたのか、自分でもわからなかった。
いつの間にか再び鳴き始めた虫の声が、遠く聞こえていた。