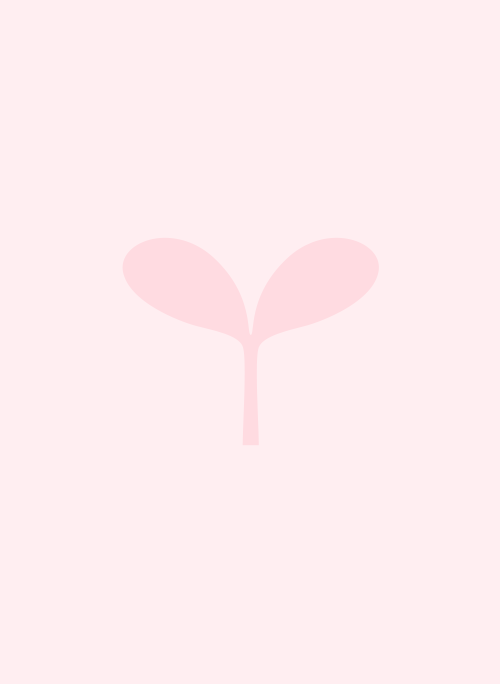何とも言えない表情をして、円士郎が黙り込む。
あの、と意を決した様子で女中が口を開いた。
「用がお済みでしたら、その……」
ちらちらと円士郎を気にしながら言う女中に、「そうだな、わかった」と私は苦笑しつつ頷いた。
どうもこの若い女中は巷の噂から、円士郎の機嫌を損ねたら何をしでかすかわからないと怯えている様子だった。
「お? なんだ、非常識だったか?」
円士郎が女中に顔を向けて微笑みかけて、女中が一瞬青くなった後──赤くなってうつむいた。
「おいおい」と私はあきれて、役者顔負けの美男子を軽く睨んだ。
「うちの屋敷の者に色目を使うのはやめてくれたまえよ」
くっくっく……と、円士郎はうつむいた女中を眺めて楽しそうに肩を揺らした。
この男は相変わらずのようだ。
「では、この辺りで別れようか」と、肩をすくめながら私は言って、白壁の途切れた分かれ道で足を止めた。
これ以上、女中をいじめてはかわいそうだし。
「旦那様は厳しい御方ですので」
女中が慌てて、言い訳のように言い添えた。
「こんなことが知れたら、お叱りを受けてしまいます」
厳しい御方、ねえ。
私と円士郎は顔を見合わせる。
さすがに外で「恐ろしい御方」とは口にしないか。
あの、と意を決した様子で女中が口を開いた。
「用がお済みでしたら、その……」
ちらちらと円士郎を気にしながら言う女中に、「そうだな、わかった」と私は苦笑しつつ頷いた。
どうもこの若い女中は巷の噂から、円士郎の機嫌を損ねたら何をしでかすかわからないと怯えている様子だった。
「お? なんだ、非常識だったか?」
円士郎が女中に顔を向けて微笑みかけて、女中が一瞬青くなった後──赤くなってうつむいた。
「おいおい」と私はあきれて、役者顔負けの美男子を軽く睨んだ。
「うちの屋敷の者に色目を使うのはやめてくれたまえよ」
くっくっく……と、円士郎はうつむいた女中を眺めて楽しそうに肩を揺らした。
この男は相変わらずのようだ。
「では、この辺りで別れようか」と、肩をすくめながら私は言って、白壁の途切れた分かれ道で足を止めた。
これ以上、女中をいじめてはかわいそうだし。
「旦那様は厳しい御方ですので」
女中が慌てて、言い訳のように言い添えた。
「こんなことが知れたら、お叱りを受けてしまいます」
厳しい御方、ねえ。
私と円士郎は顔を見合わせる。
さすがに外で「恐ろしい御方」とは口にしないか。