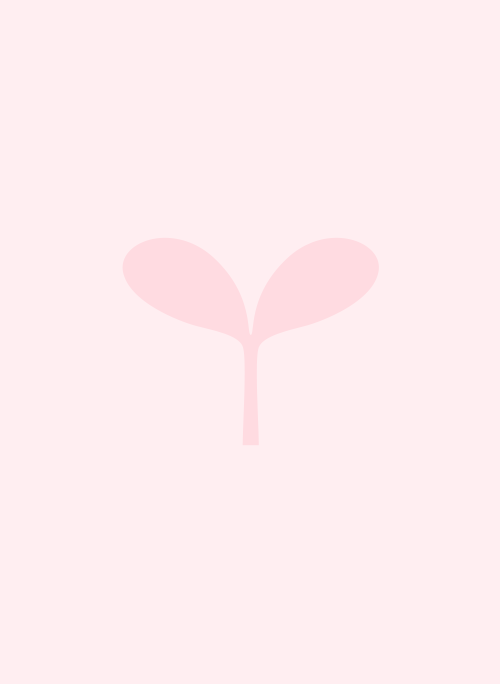この時の遊水の反応は、先の円士郎のものと同様、私が家老家の娘だということだけに対するものとは思えなかった。
しかし、ならばそれが何に根差したものなのか、私には想像できなくて、
無性に不安に駆られて、確かめた。
「遊水」
「なんだ」
「あなたは私の前からいなくなったり……しないだろう?」
「…………」
「盗賊でも、人を殺していても、あなたがどんな人でもいい。
だからまた、ここを訪ねてきてくれるだろう?」
返答をためらうかのように、遊水の目が泳いだ。
私は恐ろしくて、彼にしがみついて、
「いなくならないで……」
囁いたら、彼は私の頭を撫でて頷いた。
「わかった。俺は亜鳥の前から消えたりしない。これからもここに来るから、心配するな」
私はほっとして、
遊水の腕の中で眠りに落ちて、
次の朝、目が覚めると
遊水が円士郎によってここに担ぎ込まれたあの時と同じように、長屋の中に遊水の姿はなかった。
そしてこの日より先、彼がこの長屋に私を訪ねてくることは二度と無かった。
しかしそれは、遊水が約束を破ったのではなく──
私自身の、この長屋でのモラトリアムの時間が終わりを迎えたためだった。
私に婚儀の話が持ち上がったのは、これから間もなくのことだった。
しかし、ならばそれが何に根差したものなのか、私には想像できなくて、
無性に不安に駆られて、確かめた。
「遊水」
「なんだ」
「あなたは私の前からいなくなったり……しないだろう?」
「…………」
「盗賊でも、人を殺していても、あなたがどんな人でもいい。
だからまた、ここを訪ねてきてくれるだろう?」
返答をためらうかのように、遊水の目が泳いだ。
私は恐ろしくて、彼にしがみついて、
「いなくならないで……」
囁いたら、彼は私の頭を撫でて頷いた。
「わかった。俺は亜鳥の前から消えたりしない。これからもここに来るから、心配するな」
私はほっとして、
遊水の腕の中で眠りに落ちて、
次の朝、目が覚めると
遊水が円士郎によってここに担ぎ込まれたあの時と同じように、長屋の中に遊水の姿はなかった。
そしてこの日より先、彼がこの長屋に私を訪ねてくることは二度と無かった。
しかしそれは、遊水が約束を破ったのではなく──
私自身の、この長屋でのモラトリアムの時間が終わりを迎えたためだった。
私に婚儀の話が持ち上がったのは、これから間もなくのことだった。