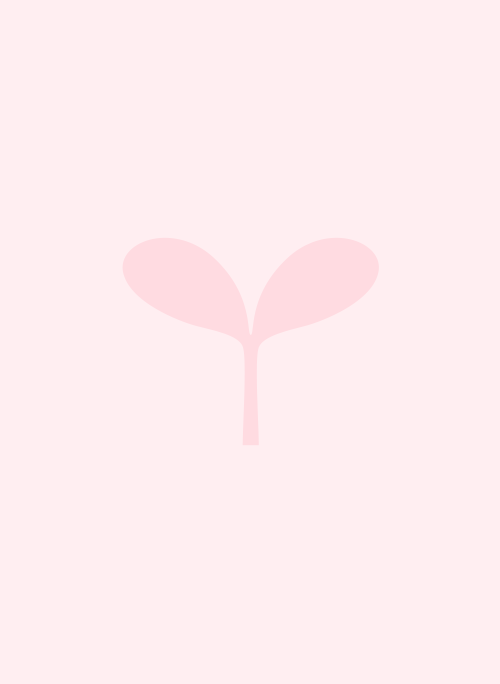この城に連れてこられて、三ヶ月ほどになるが、何だかおかしな感じなのだ。
覚悟していた拷問も陵辱もなければ、牢につながれることもない。
屈辱的だった小姓の恰好にも、いつの間にか慣れてしまった。
慣れれば動きやすく、ユーリは王子が作り上げた架空の少年になりきって暮らしている。
色々聞かれればボロが出るに違いないが、城の侍女たちも、下働きの男たちも、ユーリを遠巻きに見るだけで、積極的に話しかけてくる者は誰一人としていなかった。
書斎で本を片付けていると、二人の青年がどこからともなく現れる。
ユーリはもう慣れっこになっていて、二人のやりとりを背中でききながら、部屋中に散乱した本や書類を一つひとつ整理していきながら、迷宮に迷い込んだかのような錯覚にとらわれる。
迷宮は迷宮でも知識と情報の迷宮だ。
医学、薬学、兵学、数学、天文学、史学などの書籍に混じって、税金に関する調書や、軍備に関する資料まで転がっている。
覚悟していた拷問も陵辱もなければ、牢につながれることもない。
屈辱的だった小姓の恰好にも、いつの間にか慣れてしまった。
慣れれば動きやすく、ユーリは王子が作り上げた架空の少年になりきって暮らしている。
色々聞かれればボロが出るに違いないが、城の侍女たちも、下働きの男たちも、ユーリを遠巻きに見るだけで、積極的に話しかけてくる者は誰一人としていなかった。
書斎で本を片付けていると、二人の青年がどこからともなく現れる。
ユーリはもう慣れっこになっていて、二人のやりとりを背中でききながら、部屋中に散乱した本や書類を一つひとつ整理していきながら、迷宮に迷い込んだかのような錯覚にとらわれる。
迷宮は迷宮でも知識と情報の迷宮だ。
医学、薬学、兵学、数学、天文学、史学などの書籍に混じって、税金に関する調書や、軍備に関する資料まで転がっている。