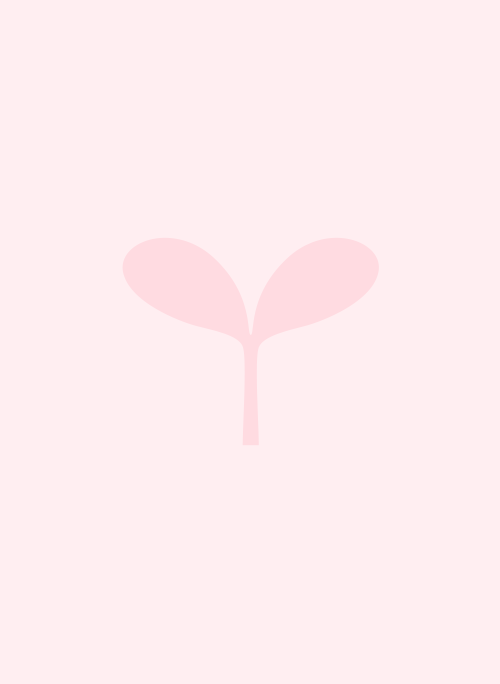「グノーがカリノ家の人間だったなんて驚きだ。平気で嘘をつけるような男じゃないから、たぶんグノー自身も最近まで知らなかったんだろう。イリア様を捕らえて処刑することが役目だったみたいだが、あいつはそれをしなかった」
「そんなことより、ずっと側にいてくれたのでしょう? どうしてそのことを教えてくれなかったの!?」
ユーリは、泣きはらした目でクリムゾンを睨みながら、甲冑の胸を両手で叩いた。
「クリムのこと、ずっと心配していたのに! そばにいてくれるってわかっていたら、イリアだって、きっと……!」
「きっと何だっていうんだ? お前を俺に託して死なれては困るんだよ!」
クリムゾンは篭手を腕から引っこ抜き、ユーリの頬を両手で挟んだ。
「ユーリ、お前だけなんだ。お前だけがあの方の世界を変えることができる!」
「できなかったわ。私、何もできなかった」
「そんなことはない!」
クリムゾンの瞳は真剣だった。
夏の海のような青い瞳から目が逸らせない。
いつも飄々としているくせに、イリアのためになら、クリムはどこまでも必死になれるのだ。
「そんなことより、ずっと側にいてくれたのでしょう? どうしてそのことを教えてくれなかったの!?」
ユーリは、泣きはらした目でクリムゾンを睨みながら、甲冑の胸を両手で叩いた。
「クリムのこと、ずっと心配していたのに! そばにいてくれるってわかっていたら、イリアだって、きっと……!」
「きっと何だっていうんだ? お前を俺に託して死なれては困るんだよ!」
クリムゾンは篭手を腕から引っこ抜き、ユーリの頬を両手で挟んだ。
「ユーリ、お前だけなんだ。お前だけがあの方の世界を変えることができる!」
「できなかったわ。私、何もできなかった」
「そんなことはない!」
クリムゾンの瞳は真剣だった。
夏の海のような青い瞳から目が逸らせない。
いつも飄々としているくせに、イリアのためになら、クリムはどこまでも必死になれるのだ。