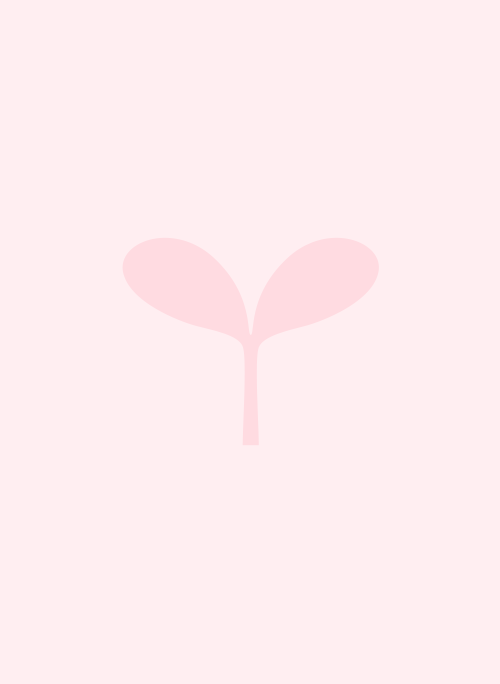「俺を刑場に連れて行け。そして、この者を開放しろ!」
扉を守っていたのは、全身銀色の仰々しい甲冑を身につけた長身の男だった。
ただの見掛け倒しかと思ったら、槍を突きつける身のこなしは、意外なほどに鮮やかだ。
「だめ、連れていかないで!」
悲鳴にも似たユーリの叫びに、軽やかな拍手の音が重なった。
あさっての方から聞こえてくるそれに一同が動きを止めた中、軽やかな足音とともに、侍女を従えて階段を降りてきたのは、燃えるような赤い髪の美女だった。
「本当にステキなお芝居だこと。観客が少ないのが残念だわ」
白い繊手が扇を優雅にひと揺らしすると、甘い薔薇の香りがふわりと漂った。
扉を守っていたのは、全身銀色の仰々しい甲冑を身につけた長身の男だった。
ただの見掛け倒しかと思ったら、槍を突きつける身のこなしは、意外なほどに鮮やかだ。
「だめ、連れていかないで!」
悲鳴にも似たユーリの叫びに、軽やかな拍手の音が重なった。
あさっての方から聞こえてくるそれに一同が動きを止めた中、軽やかな足音とともに、侍女を従えて階段を降りてきたのは、燃えるような赤い髪の美女だった。
「本当にステキなお芝居だこと。観客が少ないのが残念だわ」
白い繊手が扇を優雅にひと揺らしすると、甘い薔薇の香りがふわりと漂った。