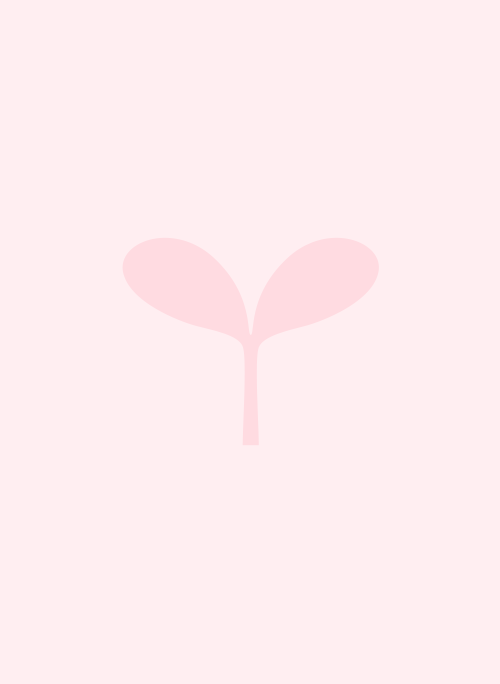「大丈夫ですから」
ちっとも大丈夫そうじゃない。
それなのに、少女は強引に微笑んでみた。
「蝋燭の予備はちゃんとあります。だから……心配しないで……」
「心配なんかしていない。明かりなんてどうでもいい」
それをよこせと手を伸ばすと、ユーリは振り切るように身を翻した。
「いい加減にしろ、もううんざりだ!」
女なのに、いや、人にかしずかれる一国の王女なのに、髪を切り、身を飾る宝石の一つもなく、こんな暗い穴倉のような場所で、お前は何をやっている?
「そこをどけ! 全て終わりにしてやる!」
ベッドから降り立ったユーリは、よろめいた途端に伸びてきた手を払いのけた。
「待って!」
すがりついてきた身体を力任せに突き放し、扉に向かう。
扉には鍵がかかっていた。
けれども、いつもユーリがしていたのを真似てノックすると、真夜中だというのに、扉の向こうで誰かが鍵を開ける金属製の音が聞こえてきた。
ちっとも大丈夫そうじゃない。
それなのに、少女は強引に微笑んでみた。
「蝋燭の予備はちゃんとあります。だから……心配しないで……」
「心配なんかしていない。明かりなんてどうでもいい」
それをよこせと手を伸ばすと、ユーリは振り切るように身を翻した。
「いい加減にしろ、もううんざりだ!」
女なのに、いや、人にかしずかれる一国の王女なのに、髪を切り、身を飾る宝石の一つもなく、こんな暗い穴倉のような場所で、お前は何をやっている?
「そこをどけ! 全て終わりにしてやる!」
ベッドから降り立ったユーリは、よろめいた途端に伸びてきた手を払いのけた。
「待って!」
すがりついてきた身体を力任せに突き放し、扉に向かう。
扉には鍵がかかっていた。
けれども、いつもユーリがしていたのを真似てノックすると、真夜中だというのに、扉の向こうで誰かが鍵を開ける金属製の音が聞こえてきた。