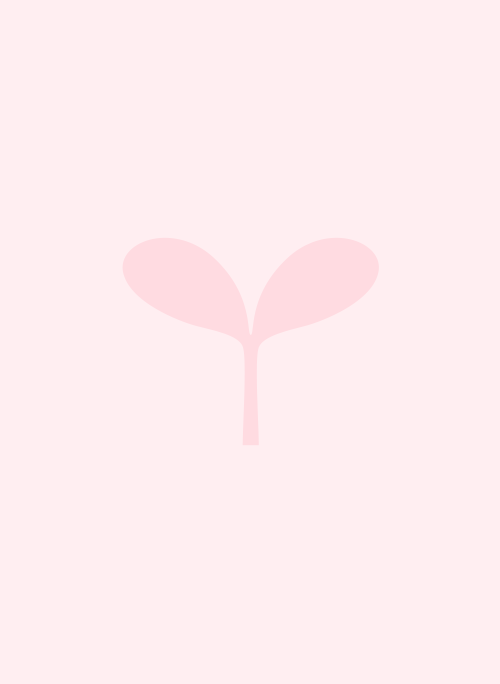「クリムゾン?!」
一方の手で木の枝をつかみ、もう一方の手に小石を持った青年が、闇の中で片頬を持ち上げて微笑んだ。
「夜這いにきてやった」
気障っぽい笑みとは裏腹に、寒さでがたがた震えている。
どけと合図されて後ずさると、音もなく部屋の中に滑り込んできた。
「慣れている感じだけど、ひょっとしていつもやってる?」
「何を?」
「夜這い」
アホかと頭をこづかれた。
「そんなことより、肺炎にでもなったらどうしてくれる!? 石を投げたら気づけよ!」
「聞こえないよ。この雨だもの」
ユーリは唇を尖らせたが、本当は泣きそうになるぐらい嬉しかった。
豪快にベッドカバーを引き剥がし、びしょ濡れのクリムゾンを頭の上から包み込んだ。
一方の手で木の枝をつかみ、もう一方の手に小石を持った青年が、闇の中で片頬を持ち上げて微笑んだ。
「夜這いにきてやった」
気障っぽい笑みとは裏腹に、寒さでがたがた震えている。
どけと合図されて後ずさると、音もなく部屋の中に滑り込んできた。
「慣れている感じだけど、ひょっとしていつもやってる?」
「何を?」
「夜這い」
アホかと頭をこづかれた。
「そんなことより、肺炎にでもなったらどうしてくれる!? 石を投げたら気づけよ!」
「聞こえないよ。この雨だもの」
ユーリは唇を尖らせたが、本当は泣きそうになるぐらい嬉しかった。
豪快にベッドカバーを引き剥がし、びしょ濡れのクリムゾンを頭の上から包み込んだ。