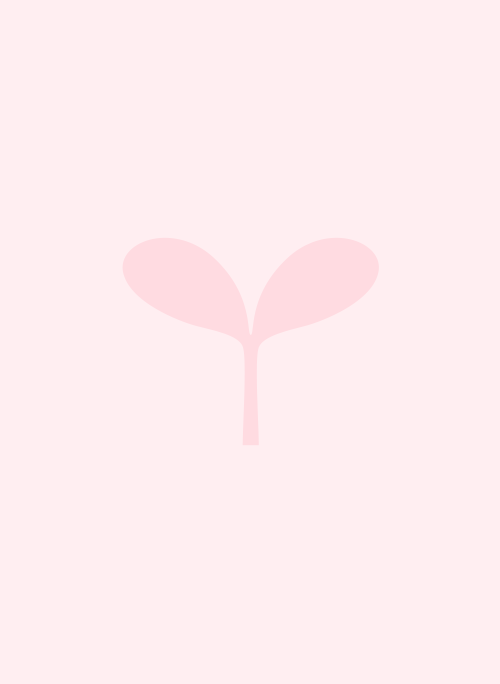一人で勝手に出かけたことについて、アランは何も言わなかった。
けれどもそれから数日のうちにユーリは郊外の屋敷に移された。
その屋敷は、資金協力してくれているという、アルミラ貴族が所有している別荘で、雑草が生い茂る外観と違い、内部はきちんと手入れされていた。
「本当にお美しいですわ」
髪を結い上げられ、細かな刺繍をほどこしたシフォンのドレスを着せられて、人形のようにソファーに座らされたユーリを前にして、シンシアはほうとため息をついた。
「まるで銀の光をまとった天使のよう。こうしてじかにお姿を拝見しておりますと、グレアム様のお気持ちが、少しだけわかる気がいたします」
降り続く雨に瞳を向けた少女の細い肩がぴくりと震えた。
「グレアムの・・・気持ち?」
物思いに沈んでいた姫君に、唐突に反応を返されて、シンシアはしまったという顔をした。
ユーリは振り返ったが、俯いたまま口を開いた相手の表情はよく見えない。
「私どもは、ユーリ様の護衛には、もっと身分の低い別の者が任じると伺っておりました。でも、ユーリ様のご意向が強くて、グレアム様に決まったのだと……。私、なんてわがままな姫君だろうと、ソニー様のご従者は、年に何度か屋敷にお戻りなのに、どうしてグレアム様は一度もお戻りになれないのかと……」
(グレアムのことが好きだったんだ)
膝の上で握り締めたこぶしにぽたぽたと涙が落ちるのを、ユーリは胸の痛みとともに見下ろした。
けれどもそれから数日のうちにユーリは郊外の屋敷に移された。
その屋敷は、資金協力してくれているという、アルミラ貴族が所有している別荘で、雑草が生い茂る外観と違い、内部はきちんと手入れされていた。
「本当にお美しいですわ」
髪を結い上げられ、細かな刺繍をほどこしたシフォンのドレスを着せられて、人形のようにソファーに座らされたユーリを前にして、シンシアはほうとため息をついた。
「まるで銀の光をまとった天使のよう。こうしてじかにお姿を拝見しておりますと、グレアム様のお気持ちが、少しだけわかる気がいたします」
降り続く雨に瞳を向けた少女の細い肩がぴくりと震えた。
「グレアムの・・・気持ち?」
物思いに沈んでいた姫君に、唐突に反応を返されて、シンシアはしまったという顔をした。
ユーリは振り返ったが、俯いたまま口を開いた相手の表情はよく見えない。
「私どもは、ユーリ様の護衛には、もっと身分の低い別の者が任じると伺っておりました。でも、ユーリ様のご意向が強くて、グレアム様に決まったのだと……。私、なんてわがままな姫君だろうと、ソニー様のご従者は、年に何度か屋敷にお戻りなのに、どうしてグレアム様は一度もお戻りになれないのかと……」
(グレアムのことが好きだったんだ)
膝の上で握り締めたこぶしにぽたぽたと涙が落ちるのを、ユーリは胸の痛みとともに見下ろした。