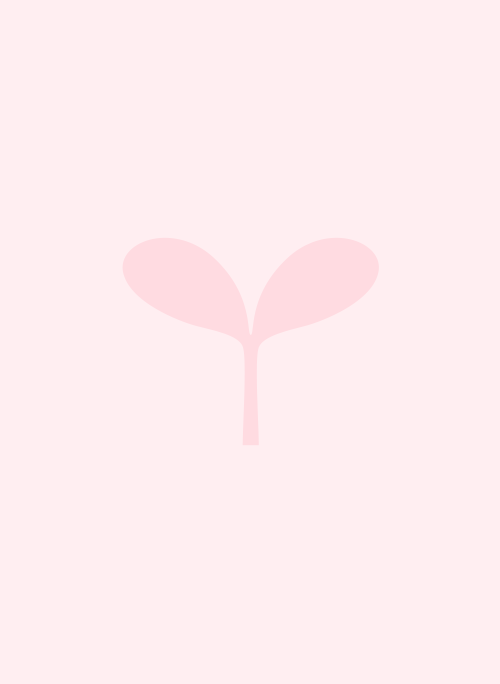髪を1つに束ねていたリボンをほどくと、銀糸のような素直な髪がさらりと流れた。
用意されていた淡い色の服に、ユーリは神妙な顔で袖を通した。
庶民の女物の服を着るのは初めてで、勝手がわからない。
胸元を飾るリボンをどうにかこうにか結び終え、ほっと息を吐き出した。
「これで、いい?」
ちゃんと着れているかどうかを確認してほしくて声をかけると、こちらに背を向けて立っていた少年が、はじかれたように振り返った。
大きく見開かれたとび色の瞳が、今度はまぶしそうに細められ、それから、はっとしたように逸らされた。
「と、とても……お美しいです」
小さな声で恥ずかしそうに告げられて、ユーリもなぜか赤くなる。
こういう反応には全く慣れていなくて、どうして良いかわからない。
「ご不便な思いをさせて申し訳ございません。でも、今しばらくの辛抱ですから」
少年の言葉に、ユーリは首を横に振る。
連れてこられた場所は、複数あるアジトの一つだというが、壁一つ隔てた隣から、他人の声が聞こえてくるような、本当に粗末な住まいだった。
用意されていた淡い色の服に、ユーリは神妙な顔で袖を通した。
庶民の女物の服を着るのは初めてで、勝手がわからない。
胸元を飾るリボンをどうにかこうにか結び終え、ほっと息を吐き出した。
「これで、いい?」
ちゃんと着れているかどうかを確認してほしくて声をかけると、こちらに背を向けて立っていた少年が、はじかれたように振り返った。
大きく見開かれたとび色の瞳が、今度はまぶしそうに細められ、それから、はっとしたように逸らされた。
「と、とても……お美しいです」
小さな声で恥ずかしそうに告げられて、ユーリもなぜか赤くなる。
こういう反応には全く慣れていなくて、どうして良いかわからない。
「ご不便な思いをさせて申し訳ございません。でも、今しばらくの辛抱ですから」
少年の言葉に、ユーリは首を横に振る。
連れてこられた場所は、複数あるアジトの一つだというが、壁一つ隔てた隣から、他人の声が聞こえてくるような、本当に粗末な住まいだった。