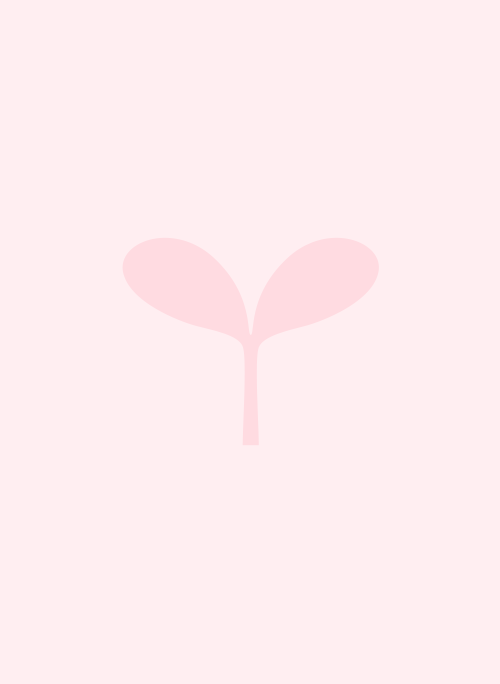「妹は重い病で、ここにつれて来られるような状態では……」
クリムゾンの話を、イリアは無言で聞いていた。
父のことも含めて、身内のことを洗いざらい話してしまったのは、王族の子にふさわしい、冷たい反応を期待してのことだった。
十一歳の子供の命を奪うことは本意ではない。
だが、血も涙もない、特権階級の人間なら話は別だ。
父親は冤罪で刑死。
母親は自殺。
妹は重い病。
貴族から平民に転落した自分。
「よくある話だ」
クリムゾンの話をみなまで聞いた後、イリアはそう結論づけた。
期待通りの反応だと思ったが、そうではなかった。
その日のうちに、妹は王立病院に移された。
妹の病室には、第四離宮の中庭で見たのと同じ花が、飾られていた。
ごくたまに、ふらりと病室に現れる黒髪の少年が誰なのか、妹は最後まで知らなかった。
「病院で迷ってしまったんですって。それで友達になったんだけど、すごくきれいな男の子でね……」
頬を染めて、目をきらきらさせて、あれは何だったのだろう?
妹は死の前日まで、イリアのことを話していた。
クリムゾンの話を、イリアは無言で聞いていた。
父のことも含めて、身内のことを洗いざらい話してしまったのは、王族の子にふさわしい、冷たい反応を期待してのことだった。
十一歳の子供の命を奪うことは本意ではない。
だが、血も涙もない、特権階級の人間なら話は別だ。
父親は冤罪で刑死。
母親は自殺。
妹は重い病。
貴族から平民に転落した自分。
「よくある話だ」
クリムゾンの話をみなまで聞いた後、イリアはそう結論づけた。
期待通りの反応だと思ったが、そうではなかった。
その日のうちに、妹は王立病院に移された。
妹の病室には、第四離宮の中庭で見たのと同じ花が、飾られていた。
ごくたまに、ふらりと病室に現れる黒髪の少年が誰なのか、妹は最後まで知らなかった。
「病院で迷ってしまったんですって。それで友達になったんだけど、すごくきれいな男の子でね……」
頬を染めて、目をきらきらさせて、あれは何だったのだろう?
妹は死の前日まで、イリアのことを話していた。