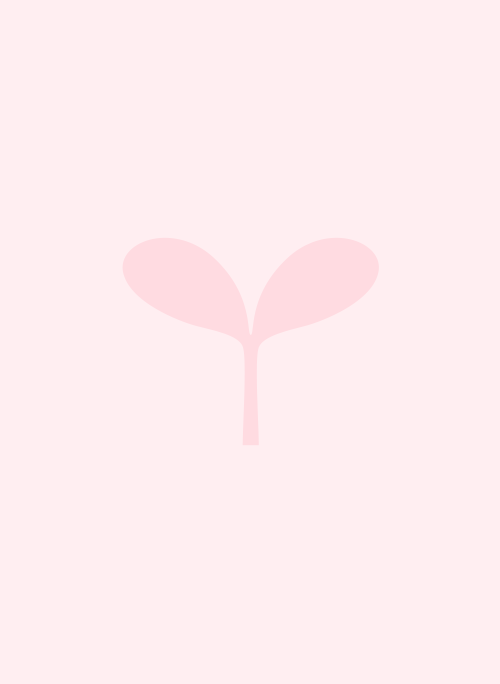「ユーリ様、大丈夫です。第四王子とその従者が王宮に詰めている今、この離宮の警護は極端に手薄です」
茫然と佇んだまま、いつまでも動こうとしないユーリを励ますように、少年が微笑んだ。
ためらいがちに伸びてきた指先が、頬の涙を優しく拭う。
兄とそっくりなしぐさに胸が痛む。
嬉しいのか、悲しいのか、それすらもわからない。
差し出された手に、自分の手を重ねた時、新しい涙がまたこぼれた。
茫然と佇んだまま、いつまでも動こうとしないユーリを励ますように、少年が微笑んだ。
ためらいがちに伸びてきた指先が、頬の涙を優しく拭う。
兄とそっくりなしぐさに胸が痛む。
嬉しいのか、悲しいのか、それすらもわからない。
差し出された手に、自分の手を重ねた時、新しい涙がまたこぼれた。