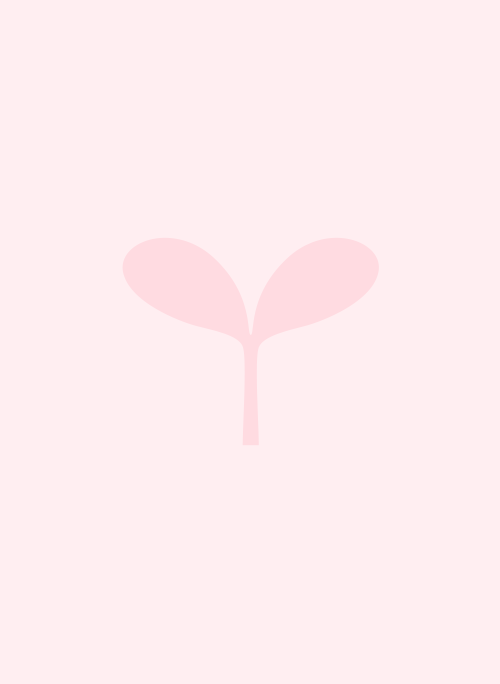大声をあげすぎたせいで、喉がひきつれたように痛かった。
擦りむいた膝小僧を涙目で見下ろしながら、ユーリはその場にへたりこんだ。
事態は何も変わらない。
いや、傷だらけになった分、さらに悪くなっている。
袋の中に放り込まれた猫が、恐慌を起こして騒ぎまわった挙句、自分で自分に爪を立てたようなものだ。
半ば放心したユーリの耳朶を打ったのは、ガチャリという金属音だった。
ユーリは声にならない悲鳴をあげたが、勢いよく扉を開けて入ってきたのはセナではなかった。
「大丈夫か!」
全力で走ってきたらしい少年に声をかけられて、ユーリはわっと泣き出した。
みっともないと思うのに、嗚咽をこらえることがどうしてもできない。
「どうしてそんなに傷だらけなんだ?」
「逃げようとして、転んで・・・」
気遣わしげな言葉に促され、どうにかこうにかそれだけ告げると、王子らしからぬ小さな舌打ちをしたイリアは、足枷の鎖を小さな鍵で難なく外し、ユーリを無言で抱き上げた。
擦りむいた膝小僧を涙目で見下ろしながら、ユーリはその場にへたりこんだ。
事態は何も変わらない。
いや、傷だらけになった分、さらに悪くなっている。
袋の中に放り込まれた猫が、恐慌を起こして騒ぎまわった挙句、自分で自分に爪を立てたようなものだ。
半ば放心したユーリの耳朶を打ったのは、ガチャリという金属音だった。
ユーリは声にならない悲鳴をあげたが、勢いよく扉を開けて入ってきたのはセナではなかった。
「大丈夫か!」
全力で走ってきたらしい少年に声をかけられて、ユーリはわっと泣き出した。
みっともないと思うのに、嗚咽をこらえることがどうしてもできない。
「どうしてそんなに傷だらけなんだ?」
「逃げようとして、転んで・・・」
気遣わしげな言葉に促され、どうにかこうにかそれだけ告げると、王子らしからぬ小さな舌打ちをしたイリアは、足枷の鎖を小さな鍵で難なく外し、ユーリを無言で抱き上げた。