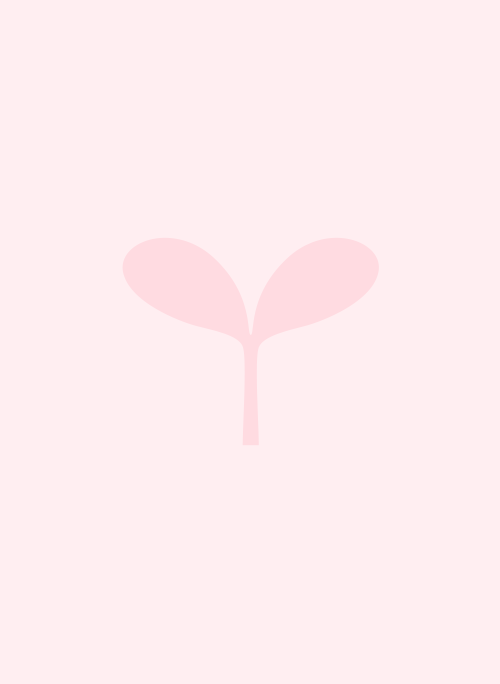唇が触れそうになって、ユーリは思いっきり顔を背けた。
「う、うまくいく、わけがないでしょ!」
怯えきった声は、なさけないほど震えていて、自分の声ではない気がした。
「うん、普通はそうだよね」
銀の髪をくるくると指に巻きつけてはほどく、単調なしぐさを飽きることなく繰り返しながら、アルミラの第三王子セナ・アルフォンソは、軽い調子で頷いた。
「さっきまでは僕もそう思っていた」
「う、うまくいく、わけがないでしょ!」
怯えきった声は、なさけないほど震えていて、自分の声ではない気がした。
「うん、普通はそうだよね」
銀の髪をくるくると指に巻きつけてはほどく、単調なしぐさを飽きることなく繰り返しながら、アルミラの第三王子セナ・アルフォンソは、軽い調子で頷いた。
「さっきまでは僕もそう思っていた」